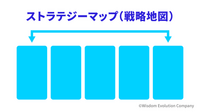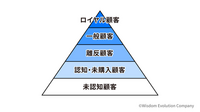※フルバージョンはこちらです
BtoBソリューションを担うパナソニックコネクトは、大企業のBtoBマーケティングにおける課題を乗り越えるため、N1分析を導入し、組織の変革を実現しました。 伝統的な「プロダクトアウト」の考え方が強かった大企業が、いかに顧客起点の組織へと変貌を遂げたのか、CMOの山口有希子氏と、マーケティングの現場で指揮を執る関口昭如氏にうかがいました。 インタビユーイー/山口有希子(やまぐち・ゆきこ)氏 パナソニックコネクト株式会社取締役執行役員シエア・ヴアイス・プレジデントCMO。シスコシステムズ、ヤフージャパンなど複数の企業にてマーケティング部門管理職に25年以上従事。日本アイ・ビー・エムにてブランド部長およびデジタルコンテンツマーケティング&サービス部長を経て、2017年より前身のパナソニックコネクティッドソリユーションズに入社。国内外のマーケティング組織・機能を強化しつつ、企業トランスフォーメーションをドライブしている。日本アドバタイザーズ協会デジタルメディア専門委員長 ad:tech tokyoアドバイザリーボード、「MASHING UP」アドバイザリーボード。 インタビューイー/関口昭如(せきぐち・あきゆき)氏 パナソニックコネクト株式会社デザイン&マーケティング本部デジタルカスタマーエクスペリエンス エグゼクティブ(兼)統括部長(兼)モバイルソリューションズマーケティング部シエアマネージャー(兼)IT・デジタル推進本部 CX総括。日立に入社後、ルネサスエレクトロニクスなどのBtoB製造業において、デジタルを中心とした、グローバルマーケティング、デマンドジエネレーションを牽引。2018年よりパナソニックコネクトにて、デジタルマーケティングカスタマーエクスペリエンス改革を断行中。また国立大学院等の教育機関にて教鞭も執る。博士。 |
伝統的な「売れる仕組み」を変え始めた
山口氏が入社した当時、パナソニックコネクトには「いいものをつくれば売れる」というプロダクトアウト的な発想が強く、マーケティングは重要視されていませんでした。現場では、決められたプロセスを回すことに注力しすぎた結果、顧客を解像度高く見ることができない状況が発生していました。
関口氏のチームは、「絶対に取れる」と言われた顧客を失注した経験などを通じ、社内に危機感を共有していきます。この危機意識を持つマネジメント層や現場の人間が繋がり、西口氏のサポートも得ながら、N1分析をテコに組織全体を動かしていったのです。潜在的な離反顧客の数が明確になるにつれ、「このままではまずい」という共通認識が社内に広がりました。
「ダントツの強み」は平均値ではなく外れ値にあった
N1分析の本質は、定量調査では見逃されがちな「異常値」や「外れ値」に注目することにあります。BtoBでは、こちらがロイヤル顧客だと捉えていても、実際は便益を感じていない「消極的なロイヤル顧客」が多く存在します。
N1分析で出てきた「意外な話」を社内で共有すると、「そんなことが使ってくださる理由だったのか」と関心が高まりました。
具体的な例として、法人向けモバイルPC「レッツノート」の有線LANポートが挙げられます。レガシーと見なされがちなこの機能が、「通信速度の安定性」や「セキュリティの担保」といった点で、お客様から「ダントツの強み」だと評価されていたのです。この発見は、誰もが知る便益よりも、N1分析で見つけた強みを伝える方が合理的であるという認識を広げる大きなきっかけとなりました。

じつは顧客をよく知るSEやCS部門を覚醒させた「レビュー会」
変革の大きな転機となったのが、「レビュー会」の重要性の認識です。このレビュー会には、営業や企画だけでなく、SEやCSなど、あらゆる職能の人が集められました。
驚くべきことに、お客様のことを一番わかっていたのは、トラブル時に訪問するSEでした。お客様はSEにネガティブな状況を話し、解決に導かれることで、SEが最も信用できる存在となっていたからです。
レビュー会ではSE部門が持つ貴重な情報が共有され、SE部門に「自分たちはこんなにお客様のことを知っている」という意識が目覚め、裏方意識から脱却しました。このレビュー会を機能させるため、マーケティング部門はインタビュー時間の5倍をレビューにかけて議論を深め、部門間の連携を強化していきました。
なぜ失注した? 複雑なステークホルダー構造を解き明かす
BtoBマーケティングの複雑さは、選定者とエンドユーザー、そして意思決定者といった複数のステークホルダーがいる点にあります。N1分析では、表面的な要望(例:「メモリを増やしてほしい」)で終わらせず、「なぜそれが必要なのか」「その目的は何か」という目的ベースで深掘りします。
また、失注分析(不採用理由の聞き取り)では、お客様が配慮から「価格が高い」としか言わないケースが多く、真の理由である「価格に見合う便益が伝わっていなかった」という本質を見抜くことが重要です。「レッツノート」の堅牢性という便益も、米警察の事例から「熱に強いこと」や「両極端な環境でも動くこと」といった具体的な使用場面と目的**を聞かなければ、真の価値は理解できません。
同社ではN1分析で見つけた特殊な便益を営業に伝え、お客様に響くかを検証する「仮説検証」のプロセスを、CRMプロジェクトの一環として導入し始めており、デジタルマーケティングにおけるABテストをリアルで行うような試みを始めています。
経営の軸にN1を CMOが目指す「会社全体を良くする」変革
樋口泰行CEOも「顧客視点」を重視しており、N1分析によるV字回復という結果が出たことで、「N1」は経営会議や取締役会の資料にまで登場し、全社的な支持を得ています。
山口氏は、CMOの役割を単なる販売促進に留めず、「会社をより良くするCMO」と捉え、カスタマーエクスペリエンス(CX)とエンプロイーエクスペリエンス(EX)の両方の向上を目指しています。CXを生み出すためには、設計・製造・営業などの機能すべてをつなぐことが必要であり、CMOがそのハブの役割を担っています。
カルチャー改革の目的は、大企業病から脱却し「お客様に近づく」意識をつくること。それが結果的に従業員一人ひとりの自立と尊重(EX)に繋がります。「お客様」という軸を真ん中に置くことで、カルチャー改革とマーケティング改革が両極から噛み合い、同社の実践はBtoBマーケティングの理想像に近づきつつあります。
※フルバージョンはこちらです
まだ会員登録されていない方へ
会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です