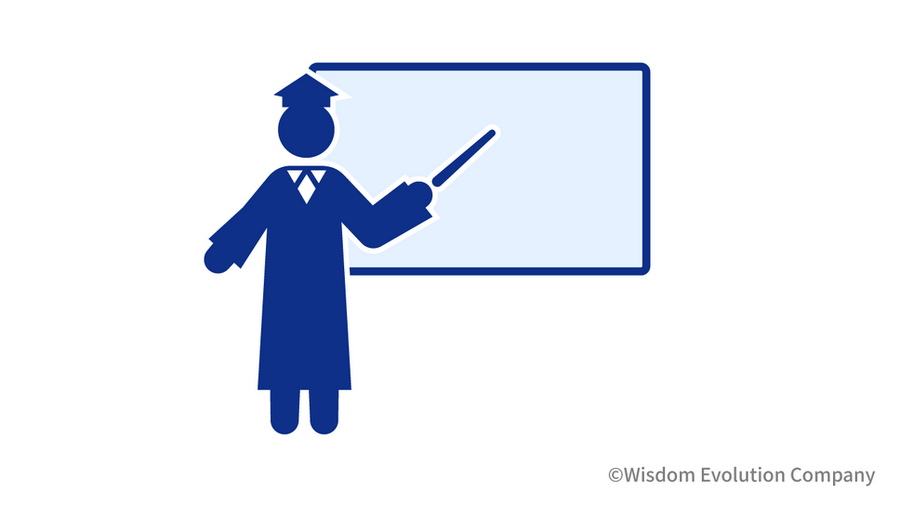
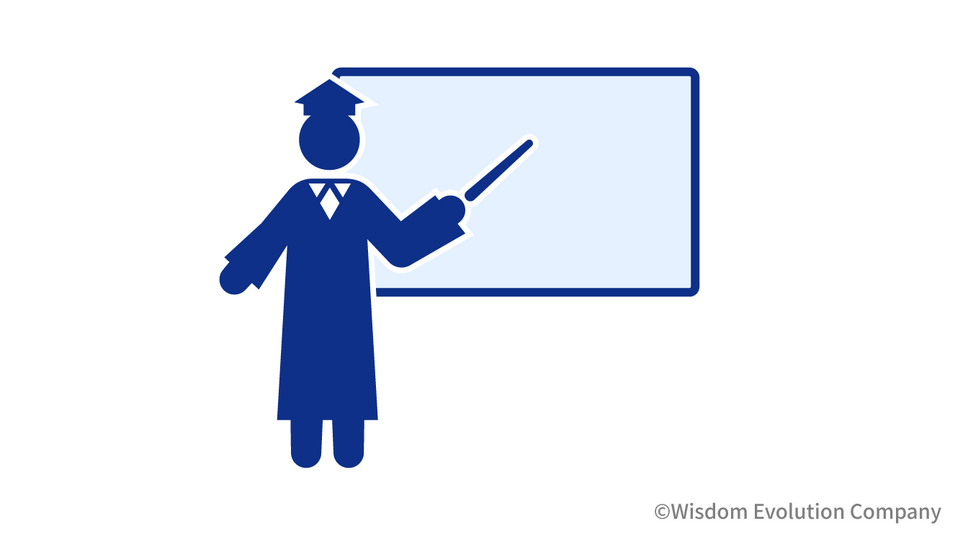
プロダクト自体に価値があるわけではない
ここまで、顧客戦略のフレームワークを解説してきました。WHOとWHATが大切だということは、多くの方が耳にしてきたことでしょう。顧客戦略の本質は本プロジェクトのオリジナルではなく、複数の先達が明文化していることを手がかりにフレームワーク化したものです。
経営学者のピーター・ドラッカー氏は「企業と使命と目的を定義するとき、出発点は一つしかない。顧客である」(『現代の経営』ダイヤモンド社)と洞察しています。マイケル・ポーター氏も「競争の本質は競合他社を打ち負かすことではなく、価値を創造することである」(『マイケル・ポーターの競争戦略』早川書房)と語り、「戦略の目的は、あらゆる顧客を幸せにすることではありません。戦略を立てるからには、対象とする顧客とニーズを定めなくてはならない」(「ハーバードビジネスレビュー」インタビュー・2011年より)と強調しています。
さらにポーター氏は「対象とする顧客とニーズを定めるべし」と繰り返し述べていますが、これはまさに顧客(WHO)と、その顧客が価値を見いだすプロダクトの便益と独自性(WHAT)を定めることです。そして、WHO・WHAT・HOWのコンセプトは、P&Gが1990年代に開発し世界中で実践しているものです。
日本には“ものづくり信仰”ともいえる、プロダクトを磨き上げる文化が根強く、それによって昭和の成長を実現しました。それ自体は現在においても誇るべき強みですが、一方で「プロダクトそのものが価値を持つのだ」という考え方に縛られているという見方もできます。
プロダクト自体に価値があると考えている限り、競合に顧客を奪われたときに取りうる策は「プロダクトを強化する/機能を追加する」ことしかなくなります。その場合、打ち出し方やWHOを転換することで拡販の余地があったとしても、そうした策があることに気が付かないため、転換を実行して拡販を実現することはできません。そして、ますます顧客が見えなくなっていきます。
顧客戦略を共有し、組織の縦割り化を解決する
ここまで強調してきた「誰に対してどんな便益と独自性を提供して価値を生み出すのか」という顧客戦略は、開発戦略、営業戦略、マーケティング戦略を含む経営上の戦略議論の上位概念になります。
組織の形態、開発戦略、営業戦略、人材戦略、生産調達戦略、そしてマーケティングやカスタマーサービスも、すべては、新しい価値の実現、すなわち顧客戦略の実現手段です。そもそも顧客戦略が明確になっておらず、組織内に共有されていないと、顧客と顧客に提供すべきことの優先順位を正しくつけることができません。すると各部門は、それぞれの専門性や機能を突き詰めることしかできず、縦割り化、サイロ化が進みます。その状態のまま組織が肥大化し続ければ、全体としてまとまりません。この問題は組織課題として扱われますが、顧客戦略を組織内で可視化、共有化することで解決できるのです。
まだ会員登録されていない方へ
会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です















































