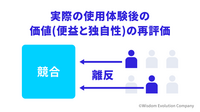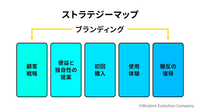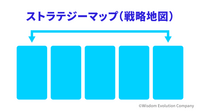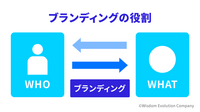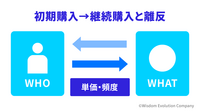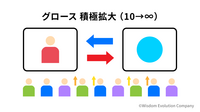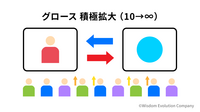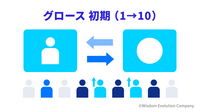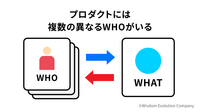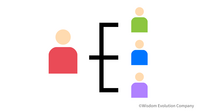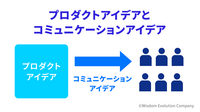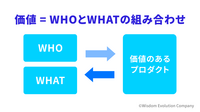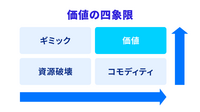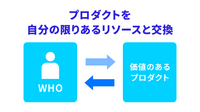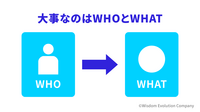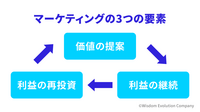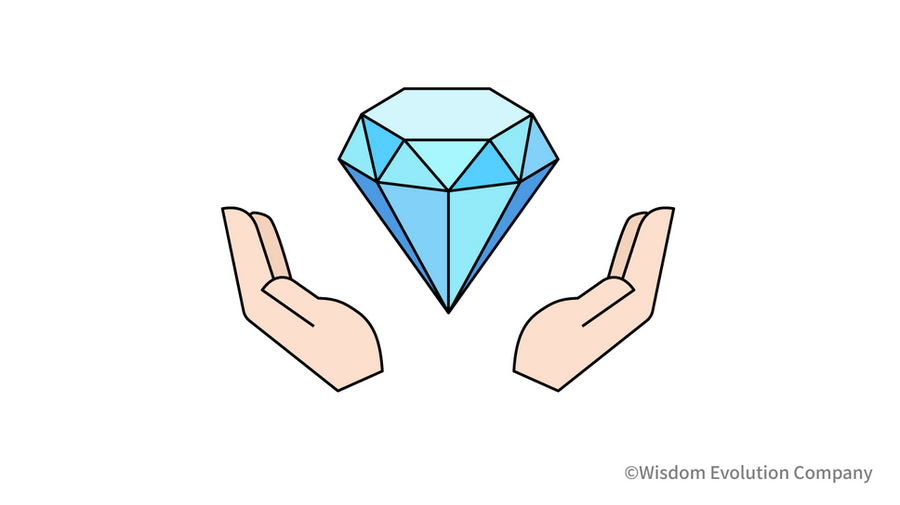
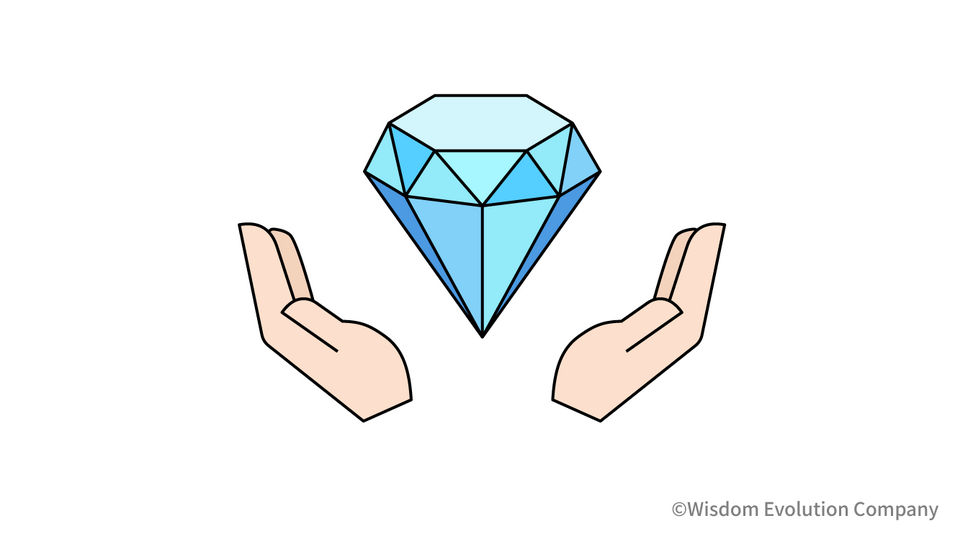
都合のいいところだけを切り取っても、ブランディングは奏功しない
「ブランディング」とは、どんな便益とどんな独自性があるかが顧客に伝わって初めてできるものであり、ある意味では「結果」の産物といえます。例えば、スターバックスコーヒーの「くつろげる場所」というイメージも創業当初からあったわけではなく、スターバックスが顧客の反応を見ながら少しずつ構築していったものです。スターバックスのようにソファーを置いて店内を落ち着いた空間にしたり、スタッフがフレンドリーな接客をしたりすればサードプレイスができる、それがブランディングだという言説もありますが、そう単純なものでもありません。
スターバックスの成り立ちを考えてみると、そのことがよくわかります。ハワード・シュルツ氏が創業したスターバックスは、もともとコーヒー豆を焙煎(ばいせん)して販売するビジネスでした。その後、シュルツ氏は豆の販売だけではなく、カフェ業態も提案します。彼は仕事でイタリアを訪れた際、エスプレッソのスタンディングバーで楽しそうに会話をしながらコーヒーを飲む人たちを見て、スターバックスでもこうした事業を展開しようとしたのです。そのため、スターバックスも最初はスタンディングで、ソファーもなく、落ち着ける店でもありませんでした。そして、それまで薄いコーヒーが主流だったアメリカでは、スターバックスの深煎りした濃いコーヒーがおいしいと評判になります。
しかし会社としては、やはり豆の販売を主体にしたかったため、シュルツ氏はスターバックスを辞めてエスプレッソ系のコーヒーを提供する別の店を始めます。そこでもまだスタンディングで、テイクアウトが主体でした。これが若い人々に受け入れられ、シュルツ氏は次々と店舗をオープンしていきます。さらにスターバックスの商標登録を買い取り、スターバックスのブランドで店舗を拡大していったのです。
時間をかけて価値を磨き上げたスターバックス
スターバックスのコーヒーの特徴は、顧客のオーダーを聞いてから豆を挽き、エスプレッソ方式で抽出して提供するというところです。ただし、そのほうが味はよくなりますが、顧客を待たせることになります。そして、その時間をただ待たせているだけでは、顧客は退屈してしまいます。そこでスターバックスは、その待ち時間を快適に過ごしてもらえる方法を考えました。店内を広くして、ソファーなどを置いて落ち着いた空間にするとか、テラス席を設ける、テイクアウト用のカップに顧客の名前を書いて親しみを表現する、サードプレイスという概念をスタッフに持たせるなど、この空間にいること自体が快適だと感じてもらえるような店づくりを目指したわけです。何かをただ待つ時間は苦痛になることもありますが、コーヒー豆を挽くよい香りも、そうしたストレスをやわらげてくれます。
こうした様々な施策の結果として、スターバックスの店舗は顧客にとって落ち着ける場所になっていきました。コーヒーのおいしさと居心地のよさを楽しむ一連の体験は最初からあったわけではなく、顧客の価値を求め、時間をかけて磨き上げていったのです。
また、スターバックスはオフィス街を中心に店舗を構え、ビジネスパーソンにホッと落ち着ける場所を提供しています。さらにアメリカではバーンズ&ノーブル、日本では蔦屋書店と提携して書店の中に店舗を出し、多くの店舗では無料Wi-Fi を導入してパソコンやスマホがインターネットにつながりやすいようにしています。
何が価値になり得るかを考え抜き、考え続ける
このようにスターバックスはいろいろな施策を行っていくなかで、顧客にとっての価値が高まる方法を考え抜いた結果、今に行き着いたわけです。つまり、スターバックスが成功した理由は、顧客の反応を見ながら「何が顧客にとって価値になり得るか」を考え続けてきたことです。様々な変化をしながら、顧客に対して自分たちがどのような価値を提供することでお金をいただけるかを常に試行錯誤し、継続的な収益を生み出すために、価値を高め続ける努力をしているということでしょう。
スターバックスは今後も進化し続けるでしょうが、このような価値づくりの変遷を理解せずに結果として成立しているブランディング部分だけを切り取って、その真似をしても、同じようにうまくはいかないはずです。それぞれの企業が、自分たちはどんな便益や独自性を提供できるのか、それを価値と感じてくれる顧客にどう伝えるのかということを考えなければ、ブランディングは成功しないのです。
まだ会員登録されていない方へ
会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です