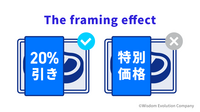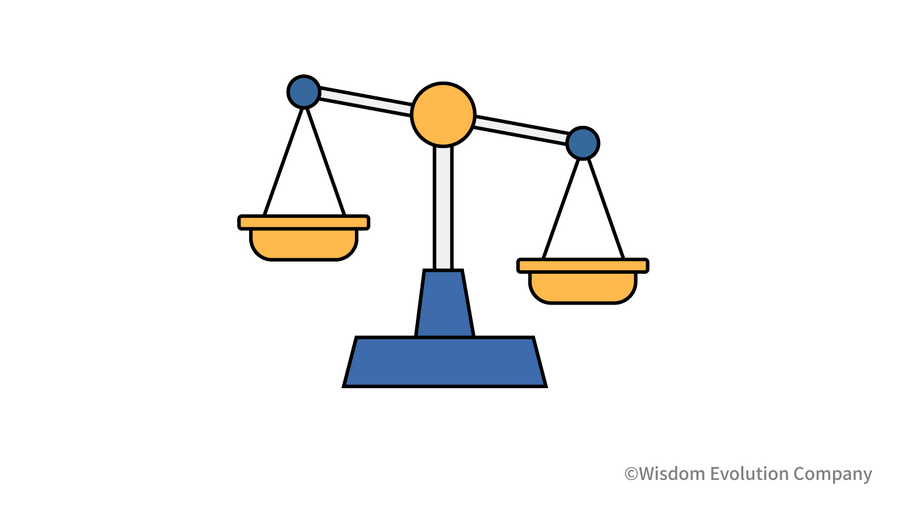
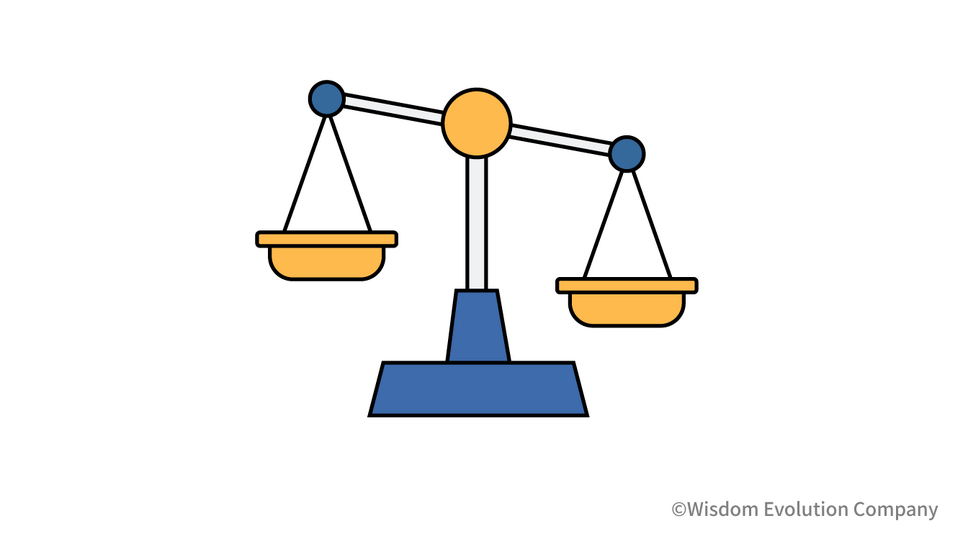
心理学の9分類に続き、優先して理解しておきたい64の理論を事例を交えながら解説します。先の9分類で代表的な理論として挙げたものも含みます。
本項では優先すべき理論28~30として、損失回避の原理、損得フレーミング、代表性ヒューリスティックを解説します。
損失回避の原理(Loss Aversion Principle)
損失回避の原理とは、人が利益を得るよりも損失を避けることに強く反応する傾向があることです。同じ価値の利益と損失では、損失の方が心理的に大きく感じられるため、利益を得る行動より損失を避けるための行動を優先します。
限定時間セール:期間限定の割引やセールを実施し、今買わないと損をするという顧客の感覚を利用します。「今だけ50%オフ! この機会を逃すと通常価格に戻ります」という広告を出し、顧客に「今買わないと損をする」というプレッシャーを与え、購入を促します。
無料お試し期間の提供:製品やサービスの無料お試し期間を設け、その後の有料化を告知することで、無料期間を逃すことを損失と感じさせます。ストリーミングサービスで「1カ月無料お試し」を提供し、期間終了後に自動更新されると告知することで、早めの登録を促進します。
バンドル販売:複数の商品をセットにして割引価格で提供し、個別に買うと損をするように感じさせます。スキンケア商品をセットで販売し、「セット購入で20%オフ! 個別に買うよりお得です」と宣伝することで、バンドル商品を選ぶよう促します。
損得フレーミング(Loss-Gain Framing)
損得フレーミングとは、同じ情報でも、提示の仕方によって顧客の受け取り方が変わる現象です。ポジティブなフレーム(得)とネガティブなフレーム(損)で同じ事実を異なる視点から提示することで、意思決定に影響を与えます。
健康食品の効果説明:製品の効果をポジティブな視点から説明します。「このサプリメントを飲むと免疫力が30%向上します」というポジティブな効果を強調することで、顧客の購入意欲を高めます。
節電商品の広告:省エネ製品のメリットを、損失の回避として提示します。「このエアコンを使うと、月々の電気代が20%減ります」という、今までの無駄遣いを減らせるという視点で訴求します。
保険商品の説明:保険の必要性を、損失の視点から説明します。「この保険に加入しないと、事故の際に全額自己負担になります」といったネガティブなフレームで説明し、加入の動機を強めます。
代表性ヒューリスティック(Representativeness Heuristic)
代表性ヒューリスティックとは、人が物事を判断する際に、典型的なイメージや過去の経験に基づいて判断する傾向です。直感的に、ある対象がどれだけ「代表的」であるかに基づいて確率や頻度を評価します。
ブランドイメージの強化:自社製品が、ブランドの典型例であることを強調します。高級車メーカーが「我が社の車は、成功者の象徴です」と宣伝し、ブランドイメージを強化することで、顧客がその製品を選びやすくします。
類似商品との比較:競合製品と自社製品の代表的な特徴を比較して、自社製品の優位性を強調します。「この洗剤は、他社製品と比べて汚れ落ちが2倍速い」という広告を出し、顧客が自社製品を選ぶように促します。
顧客の典型的なイメージの活用:自社製品が、対象顧客にとって典型的であることをアピールします。「忙しいビジネスパーソンのためのエナジードリンク」として宣伝し、対象顧客層が「自分に合った商品だ」と感じるよう促します。
まだ会員登録されていない方へ
会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です