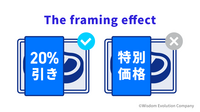心理学の9分類に続き、優先して理解しておきたい64の理論を事例を交えながら解説します。先の9分類で代表的な理論として挙げたものも含みます。
本項では優先すべき理論25~27として、選択過多、選択支持バイアス、ソーシャルプルーフを解説します。
選択過多(Choice Overload)
選択過多とは、選択肢が多すぎると、かえって決断が難しくなり、ストレスや不安を感じる現象です。多くの選択肢があると、顧客はどれを選べばいいのか迷ってしまい、最終的に選択を避けることさえあります。
製品ラインナップの整理:商品やサービスのラインナップを整理して、顧客が簡単に選択できるようにします。スーパーでのヨーグルトの種類を10種類から5種類に減らすことで、顧客が選びやすくし、購入を促進します。
ガイド付き選択:顧客のニーズに合わせたガイドを提供し、選択肢を絞る手助けをします。 家電量販店で、購入ガイドを提供し、使用目的に応じたおすすめの製品を3つに絞って提案することで、選択の負担を減らします。
トップピック(おすすめ商品)の提示:人気商品や推奨商品を目立たせ、顧客の選択を容易にします。オンラインストアで「ベストセラー」や「スタッフのおすすめ」といったラベルをつけて目立たせることで、顧客が選びやすくなります。
選択支持バイアス(Choice-Supportive Bias)
選択支持バイアスとは、一度選択したものを肯定的に評価し、選ばなかったものに対して否定的な評価をする傾向です。選択後、選んだものが正しいと信じ込むことで、選択の正当性を確保しようとする心理です。
購入後のアンケート:購入後にポジティブなフィードバックを得るためのアンケートを実施し、顧客が選択を支持するよう促します。「この製品に満足していますか?」というアンケートを送付し、肯定的な評価を集め、それを公表することで他の潜在顧客に対してもポジティブな印象を広めます。
アフターサービスの強調:購入後のアフターサービスを充実させ、顧客が選択を後悔しないようにします。家電製品を購入した顧客に対して、無料の設置サービスやカスタマーサポートを提供し、選択に満足感を抱くよう促します。
ロイヤリティプログラムの導入:リピーター向けのロイヤリティプログラムを導入し、選択の正当性を強化します。レストランで会員カードを発行し、来店ごとにポイントが貯まり、特典を得られるようにすることで、顧客の選択を肯定的に感じさせます。
ソーシャルプルーフ(Social Proof)
ソーシャルプルーフとは、人が他人の行動や意見を参考にして、自分の行動や意思決定をする現象です。多くの人が利用しているものや、信頼できる人が推薦するものを選びやすくなります。
インフルエンサーマーケティング:インフルエンサーに製品を紹介させます。美容情報の提供で人気のインフルエンサーに自社製品をレビューしてもらい、そのフォロワーが同じ製品を購入するよう促します。
ユーザーレビュー:顧客のレビューや評価を強調します。オンラインショップが「この商品は500人以上のユーザーが5つ星評価!」と表示し、他人の意見に基づいて購入を決定するよう促します。
顧客数の表示:多くの人が利用していることを示します。サブスクリプションサービスが「100万人が利用中!」と広告に表示し、多くの人が信頼していることをアピールして新規顧客を獲得します。
まだ会員登録されていない方へ
会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です