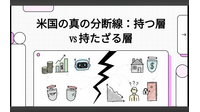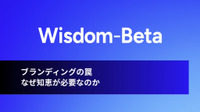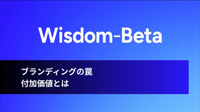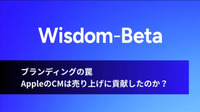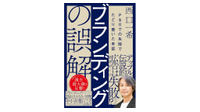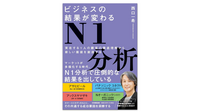経営の新たな主戦場と罠
現代の企業経営において、「人的資本経営」という言葉がバズワードのように飛び交っています。知識集約型社会への移行、産業構造の変化、労働人口の減少という構造的な圧力の中で、人的資本が競争優位の源泉であることは疑いようがありません。多くの企業が人材投資の重要性を叫び、統合報告書には「体系的な研修制度」「先進的な福利厚生」といった美辞麗句が並びます。
しかし、その実態はどうでしょうか。制度は整えた、予算も投じた。それでも期待したほど人は育たず、イノベーションは生まれず、優秀な人材の離職は止まらない。多くの経営者が直面するこの現実は、人的資本経営が「成果なき投資」、すなわち「見せかけの投資」という深い罠に陥っていることを示唆しています。
私(筆者)は、新卒の1990年から2006年までの16年間、プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)という組織の内部に身を置いていました。当時は「人的資本経営」などという言葉は存在せず、ただ、組織の哲学に基づき、ビジネスの成長と人材の育成を当然のこととして追求していました。
昨今、この人的資本経営の潮流を理解し、多くの企業がその実践に苦慮している現状を目の当たりにするにつれ、ある確信に至りました。世間が今、新しい概念として追い求めている「人的資本経営の理想」とは、P&Gが180年以上にわたり、当たり前のように実践し続けてきた経営そのものだったのではないか、と。P&Gを離れて20年も経つので、現在のP&Gの実態と同じかどうかわかりませんが、少なくとも一つの理想的とも思える「人的資本経営」の事例としてまとめてみます。
P&Gでの経験は、人的資本経営が決して短期的な施策や流行りのテーマではなく、「人と組織の潜在能力を戦略的に最大化し、いかにして中長期的な企業価値の向上に直結させるか」という、経営戦略の中核そのものであることを教えてくれました。
この解説記事は、現代経営が陥っている「見せかけの人的投資」という罠を分析し、いかにして回避するかを探求するものです。その道標として、私が内部で経験し、その強さの源泉を肌で感じてきたP&Gの哲学と実践に焦点を当てます。これは単なる事例紹介ではなく、企業が人材を軸に競争優位を維持する「仕組み」とは何かを、内部からの視点を交えて解き明かす試みです。
人的資本経営の本質と時代の要請
まず、私たちが目指すべき「人的資本経営」とは何か、その本質と背景を明確に理解することから始めなければなりません。
人的資本経営の定義:コストから資本へ
人的資本経営とは、従業員を単なる労働力(コスト)として管理するのではなく、企業価値を生み出す源泉たる「資本(Capital)」として捉える経営思想です。それは、従業員が持つ知識、スキル、経験といった個人の能力だけでなく、エンゲージメント(自発的貢献意欲)、創造性、リーダーシップ、そして組織文化といった目に見えない資産までを含めた総合力を、戦略的に最大化しようとするアプローチです。
これは、従来型の「人事労務管理」とは根本的に異なります。人事労務管理が「いかに効率的に人を管理・運用するか」という視点に立つのに対し、人的資本経営は「いかに戦略的に人に投資し、そのリターン(企業価値向上)を最大化するか」という視点に立ちます。すなわち、経営戦略と人材戦略が不可分に統合されている状態を指します。P&Gでは、この統合は議論の余地がないほど自明のことでした。
なぜ今、不可欠なのか:3つの構造的要因
この思想が急速に広がった背景には、不可逆的な3つの構造的要因が存在します。
(1) 人口動態の変化と生産性向上の絶対的必要性
日本は、深刻な少子高齢化と人口減少に直面しています。生産年齢人口の減少は、採用数の拡大によって組織の成長を維持する「量的拡大モデル」の終焉を意味します。企業の存続条件は、限られた人材一人ひとりの生産性を最大化し、新たな価値を創出する「質的向上モデル」への移行以外にありません。
(2) 資本市場からの強い圧力とガバナンス改革
投資家の企業評価基準も決定的に変化しました。現代の知識経済社会においては、有形資産よりも無形資産(人的資本を含む)の重要性が飛躍的に高まっています。日本でも、コーポレートガバナンス・コード改訂や、2023年3月期決算からの有価証券報告書における人的資本情報の開示義務化など、制度改革が急速に進みました。企業はもはや、投資の「有無」だけでなく、その投資が経営戦略とどう連動し、どのような成果に結びついているのかを説明する責任を負っています。
(3) 市場評価メカニズムの変化(ESG投資の潮流)
人的資本を重視する経営姿勢が、株式市場における評価に直結する仕組みが広がっています。ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の潮流の中で、人的資本は「S(社会)」の重要な要素として位置づけられています。
成果なき投資の根本原因 – 曖昧な期待値と設計の欠陥
時代の要請は明白であるにもかかわらず、なぜ多くの企業で投資が成果に結びつかないのでしょうか。その根本原因は、「曖昧な期待値」と「設計の欠陥」という、二つの重大な誤謬にあります。これは、P&Gでの経験に照らすと、極めて明確に見えてくる構造的な問題です。
誤謬①:曖昧な期待値 – 「満足度」と「エンゲージメント」の混同
多くの企業が犯す最初の、そして最も致命的な間違いは、人的資本投資の成果指標(KPI)を「従業員満足度(Employee Satisfaction)」に置いてしまうことです。
従業員満足度とは、主に給与水準、福利厚生、職場の快適さといった「環境」や「待遇」に対する評価です。これらは経営学者フレデリック・ハーズバーグが提唱した「衛生要因」に相当し、不満足を防ぐ効果はあっても、積極的な動機付けにはなりません。満足度を高めることは離職率の低下には寄与しても、生産性の向上やイノベーションの創出を保証するものではないのです。「快適だが、挑戦はしない」組織を生み出すリスクさえあります。
人的資本経営が本来目指すべき成果指標は、「従業員エンゲージメント(Employee Engagement)」です。エンゲージメントとは、従業員が自社のビジョンや仕事の意義に深く共感し、自律的・主体的に組織の成功に貢献しようとする意欲の状態を指します。これは「動機付け要因」にあたります。
P&Gでは、待遇や環境以上に、「どれだけ挑戦的な仕事を通じて成長できるか」「どれだけ組織に貢献できるか」が重視されていました。この熱意こそが、持続的な成果創出に直結するのです。期待値の設定の違いが、投資の成果を決定的に左右します。
誤謬②:設計の欠陥 – 「点」の投資と「全体最適」の欠如
もう一つの深刻な問題は、投資の設計範囲が極めて狭く、近視眼的であることです。多くの企業が、人的資本投資を「研修=スキル強化」と短絡的に捉えています。
しかし、個人が研修で学んだ知識やスキルを職場で活かせるかどうかは、研修そのものの質以上に、その周辺環境(エコシステム)の設計に大きく依存します。
配置・異動: 習得したスキルを実践投入できる挑戦的な機会があるか。
評価・報酬制度: 新しい挑戦やスキル発揮が公正に評価され、報われるか。
マネジメント: 上司が部下の挑戦を支援し、適切なフィードバックを与えられるか(心理的安全性)。
組織文化: 失敗を許容し、新しいアイデアを歓迎する文化があるか。
これらの環境が整備されていなければ、投資は単発の「研修イベント」として消費され、経営成果には結びつきません。人的資本経営の設計は、研修という「点」ではなく、「面」としての全体最適でなければなりません。
さらに、「全社員一律の施策」も効果を希薄化させます。本来は、経営戦略に基づき、企業価値創出に直結するキーポジションや次世代リーダー層に対して重点的に投資を行うべきですが、戦略的な意図が曖昧なままでは、投資は分散し、決定的なインパクトを生み出せません。
P&Gにみる理想 – 人的資本経営を「仕組み」として実装する
こうした“罠”を回避し、人的資本経営を経営の根幹として長期にわたり実践してきたのがP&Gです。長らく「CEOファクトリー(CEO製造工場)」と呼ばれるほど卓越したリーダーを輩出し続けているその強さの秘密は、人的資本経営を個人の努力や偶然に依存せず、文化と一体化した「仕組み」として実装している点にあります。私が1990年代から2000年代にかけて目の当たりにしたのは、まさにこの「仕組み」の力でした。
哲学の根幹:「Build-from-Within(内部育成と登用)」
P&Gの人材哲学を象徴するのが、「Build-from-Within(内部から築き上げる)」という揺るぎない信念です。P&Gは、新卒で採用した人材を長期的な視点で育成し、経営幹部に登用することを基本原則としています。CEOをはじめとする経営層の大半は生え抜きの内部登用です。
これは、人材を短期的に“消費”するのではなく、長期的に“資本化”し、組織のDNAを継承していくという思想を体現しています。私が在籍していた期間も、この哲学が揺らぐことはありませんでした。この原則があるからこそ、長期的な視点での人材投資を躊躇なく行うことができるのです。
成長の設計図:「70-20-10モデル」と「Day1責任主義」
P&Gは、人の成長に関する明確な設計図を持っています。それが「70-20-10モデル」です。人の成長の70%は「業務経験」、20%は「他者からの薫陶(メンタリング・コーチング)」、10%は「研修」によってもたらされるという考え方です。当時の私の感覚では、「50-25-25」の感じでしたが、この分厚いメンタリングと社内研修は、その後、P&Gを離れた後、どの企業でも体験できないP&G独自の仕組みだったと理解しました。
P&Gは「経験」を最も重視し、それを意図的に設計しています。その具体的な実践が「Day1責任主義」です。新入社員であっても、入社初日(Day1)から、一人のプロフェッショナルとして扱われ、重要なプロジェクトやブランドの一部を担う責任と権限が与えられます。筆者が在籍した1990年代当時から、これは誇張ではなく厳然たる事実でした。私自身も、入社直後から想像を超える責任の重さに直面しました。この「ストレッチ・アサインメント(背伸びが必要な仕事の割り当て)」という修羅場経験こそが、実践の中で急速な成長を促す原動力となります。
文化の中核:「徹底したメンタリング」と「リーダー育成の責務」
経験を最大限の学びに変えるためには、「薫陶」が不可欠です。P&Gにおいて、メンタリングは単なる制度ではなく、文化として深く根付いています。上司や先輩は、業務スキルだけでなく、P&Gの価値観、リーダーシップ、長期的なキャリア形成に至るまで、深くコミットして支援します。そのコミットメントの深さは、外部から見れば異様とも思えるほど徹底しており、筆者自身もその恩恵を深く享受した一人です。これはP&Gを辞めた後にも先輩後輩と継続しており、仕組み以上の文化であり価値観なのだと実感しています。
P&Gの経営陣は、「リーダーを育成することは、経営における最重要の仕事である」と公言し、自らの時間とエネルギーを人材育成に惜しみなく投じます。当時、多忙を極めるシニアリーダーたちが、驚くほど多くの時間を部下の育成やコーチングに費やしていたことが印象的でした。この強力な支援体制があるからこそ、若手社員はDay1からの大きな責任を乗り越え、成長することができるのです。
組織のOS:「PVP(Purpose, Values & Principles)」の徹底
世界約70カ国以上で多様な人材が働くP&Gが、なぜ一つの組織として結束し、一貫した価値を提供し続けられるのか。その鍵は、組織のOS(オペレーティングシステム)とも言える「PVP(Purpose, Values & Principles:目的、価値観、行動原則)」の存在です。
P&Gは、このPVPを単なるお題目として掲げるのではなく、採用、育成、評価、日々の意思決定に至るまで、あらゆる活動の共通規範として徹底的に活用しています。PVPという共通言語があるからこそ、多様な人材が同じ方向を向き、自律的に行動できるのです。
競争優位の源泉:ビジネス成果と人材育成の「両立」を問う評価基準
P&Gの人的資本経営を最も象徴し、他の多くの企業と決定的に一線を画すのが、その評価・昇進基準です。P&Gでは、「ビジネス成果(Business Results)」と「人材育成・組織開発(Organization Building)」の両立が、昇進のための絶対条件です。
いかに圧倒的なビジネス成果を上げたとしても、部下を育成できていない、あるいは組織開発上の問題があれば、決して昇進することはありません。逆に、人材育成にどれほど優れていても、期待される業績を達成できなければ、やはり出世はできません。私の在籍中も、輝かしい業績を上げながら組織構築が苦手ななめにキャリアが停滞したリーダーを数多く目にしてきました。
この「両立基準」こそが、P&Gにおいて人的資本経営が形骸化せず、世代を超えて維持・継承されている核心的な仕組みです。私が在籍していた当時も、この基準は極めて厳格に運用されていました。経営者が「人も業績も大事だ」と口で言うのは簡単ですが、それを評価基準という最もシビアな仕組みにまで落とし込んでいる点に、P&Gの本気度と卓越性があります。今思えば、これこそが人的資本経営の神髄でした。
P&Gから導き出す、真の人的資本経営への5つの教訓
P&Gでの経験と、昨今の人的資本経営の潮流との対比から、私たちが「見せかけの投資」という罠を回避し、真の人的資本経営へと舵を切るための、普遍的な教訓が導き出されます。
教訓1:成果は「ビジネス × 人材育成」の両立で測る
最も重要な教訓は、評価・昇進基準の変革です。短期的なビジネス成果だけでなく、人材育成・組織開発への貢献を、管理職やリーダーの評価基準に明確に組み込む必要があります。これにより、リーダー層は本気で人材育成に取り組み、人的資本経営が持続可能な仕組みとなります。
教訓2:「満足度」ではなく「エンゲージメント」を追求する
成果指標の設定において、「従業員満足度」という罠から脱却しなければなりません。目指すべきは、快適さではなく、従業員の挑戦意欲や主体性を引き出す「エンゲージメント」です。ビジョンの共有、成長機会の提供、権限委譲、公正な評価を通じて、仕事そのものの魅力を高めることが不可欠です。
教訓3:設計は「点(研修)」にとどまらず「全体最適」を目指す
人材育成を「研修」という狭い範囲で捉えることをやめ、全体最適の視点で設計する必要があります。P&Gの「70-20-10モデル」が示すように、戦略的な配置・異動による実践経験と、メンタリングやフィードバック文化、それらを反映した社内研修こそが重要です。配置、評価、報酬、組織文化、教育までを含めたエコシステム全体を最適化することで、初めて投資効果が最大化されます。
教訓4:長期的なコミットメントを前提とする
短期的な施策としての人的資本経営は、必ず失敗します。P&Gが何十年以上かけて築き上げ、私が在籍した16年間も脈々と受け継がれていたように、人的資本経営は、長期的な視点に立ち、世代を超えて継承されるべき経営の基盤です。歴代の経営トップの強い信念と、一貫した投資を継続する覚悟が求められます。
教訓5:経営戦略と人材戦略を完全に不可分にする
人材戦略を、経営戦略から独立した人事部門のテーマとして扱ってはなりません。経営戦略を実現するために、どのような人材が必要かを具体的に定義し、その獲得・育成・活用のための方策を、経営戦略と完全に連動させる必要があります。事業成果と人材育成を一体化させることが、真の人的資本経営の鍵となります。
人的資本経営は「経営そのもの」である
人的資本経営の目的は、決して制度や研修プログラムを整備すること自体ではありません。昨今の潮流の中で、多くの企業が「曖昧な期待値」と「設計の欠陥」によって、貴重なリソースを「成果なき投資」に浪費しているケースを多く目にします。流行として短期的に導入した人的資本経営は、一過性のブームとして終わり、組織に深い徒労感を残すだけでしょう。
私がP&Gで体験させて頂いた一つの理想形は、「ビジネス成果の追求」と「人材育成・組織開発」を高い次元で両立させ、それを評価や昇進の基準として経営の仕組みに組み込み、文化として定着させること」にあります。それは、従業員の成長が企業の成長に直結する好循環を生み出す経営モデルです。
P&Gを離れてから約20年が経とうとしている今、かつて組織内部で「当たり前」として経験してきたことが、「人的資本経営」という新たな言葉で脚光を浴びているようで不思議な感覚です。当時体験したP&Gの実践は、流行に左右されることなく、人と組織の可能性を最大化するための普遍的な原理原則、すなわち「経営の王道」を示していたと思います。
私たちは、人的資本経営を「経営そのもの」として捉え直すべきです。それは、長期のコミットメントを前提とした、決して平坦ではない道のりだと思います。しかし、社員一人ひとりの可能性を信じ、その成長と企業の成長を一体化させる仕組みを築き上げ、それを代々継承していくことこそが、不確実な未来において真の競争優位を生み出す、唯一の道だと強く感じています。
この解説が何らかのお役に立てば幸いです。
まだ会員登録されていない方へ
会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です