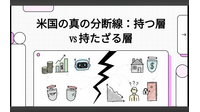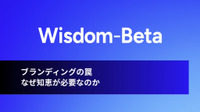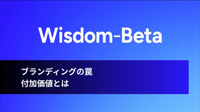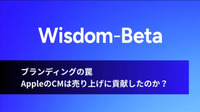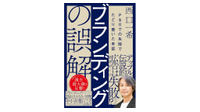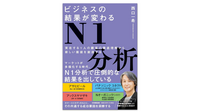組織が調和を求める罠
その「調和」、本当に顧客のためですか?
ビジネスの現場において、「合意形成」や「チームの調和」は、円滑な組織運営に不可欠な要素として尊重されます。会議では、角が立たないように意見を調整し、関係各所の顔を立てながら、穏便な着地点を探ることが賢明な振る舞いだとされることも少なくありません。しかし、その耳障りの良い「調和」という言葉の裏で、私たちが本来向き合うべき最も重要な存在、すなわち「顧客」を軽視してしまっている状況を頻繁に目にします。
顧客にとっての絶対的な価値、すなわち「何がベストか」を純粋に突き詰めていくと、組織内部の論理や力学としばしば激しく衝突します。それは、部門間の利害、短期的なKPI、そして「これまでこうやってきた」という過去の常識の壁です。この壁を乗り越えようとする情熱的な試みは、内部からは「強引」「独善的」「和を乱す行為」と映ることがあります。
この記事では、この「強引」という言葉に付与されたネガティブなレッテルを一度剥がし、その本質を掘り下げていきます。そして、安易に「調和」を求めることが、いかに企業の成長を蝕む「罠」となり得るのかを、具体的な事例を交えながら論じていきたいと考えます。結論から言えば、顧客起点を貫く上で「強引さ」は必然の推進力なのです。これまでにお会いした、結果を出し続けるビジネスパーソン、マーケターの多くは、意識しているかどうかは別として、「強引」「わがまま」とのレッテルを受け入れて、顧客への価値を徹底されています。
「強引」に見える行動の正体
なぜ、顧客にとってのベストを追求する姿勢が「強引」と見なされてしまうのでしょうか。その理由は、それが「社内事情」と「過去延長の常識」という、組織内に深く根付いた二つの慣性に正面から逆らう行為だからに他なりません。
顧客価値を阻む「社内事情」の壁
多くの企業は、機能別に最適化された部門の集合体として成り立っています。営業部門は売上目標、開発部門は開発工数と納期、マーケティング部門はリード獲得数といったように、それぞれが個別のKPIを背負っています。この構造は、各部門の専門性を高める一方で、顧客価値という共通の目標を見失わせる「部門最適の罠」を生み出します。
例えば、あるSaaS企業で、顧客から「既存の機能Aと機能Bを連携させれば、業務効率が劇的に上がる」という切実な要望が寄せられたとします。顧客に憑依し、その価値を確信したプロダクトマネージャーが、すぐさま開発部門に連携機能の実装を提案します。しかし、開発部門のロードマップは既に別の大型案件で埋まっており、リソースに余裕はありません。さらに、営業部門からは「連携機能よりも、目先のコンペで勝つための新機能Cを優先してほしい」という声が上がります。
この状況で、プロダクトマネージャーが「いや、この連携機能こそが顧客ロイヤルティを高め、長期的なLTV(顧客生涯価値)向上に繋がる最優先事項です」と強く主張すれば、どうなるでしょうか。開発部門からは「現場の工数を無視している」、営業部門からは「現場ニーズ、売上を軽視している」と反発を招き、彼は「強引でわがままな人」というレッテルを貼られることになります。しかし、彼の主張の根幹にあるのは、社内の都合ではなく、顧客の成功です。この「強引さ」は、サイロ化された組織の中で、顧客という唯一の共通言語を叫び続ける孤独な戦いなのです。
変化を拒む「過去延長の常識」という呪縛
企業には、過去の成功体験から生まれた「常識」や「暗黙のルール」が必ず存在します。それはかつて企業を成長させたエンジンでしたが、市場や顧客が変化する現代においては、むしろ足枷となることが多いのです。
ある老舗アパレルメーカーの事例を考えてみましょう。長年、百貨店での対面販売をビジネスの主軸とし、「高品質な商品を、丁寧な接客で販売する」ことが自社の成功方程式だと信じてきました。しかし、消費者の購買行動はECへとシフトし、若年層はSNSやインフルエンサーから情報を得るのが当たり前になっています。
ここで、若手のマーケターが「ECサイトへの大胆な投資と、インフルエンサーを起用したデジタルマーケティングへの転換」を役員会で提案したとします。彼の提案は、データに基づき、顧客の変化を的確に捉えたものでした。しかし、役員たちからは「我々のブランドイメージが損なわれる」「長年付き合いのある百貨店との関係はどうするのだ」「ネットの素人に我々の商品の価値が分かるはずがない」といった否定的な意見が噴出します。
この役員たちの反対は、悪意から来るものではありません。彼らは自社の成功体験という「常識」に固執しているだけなのです。この厚い壁を前に、若手マーケターがデータを突きつけ、何度も粘り強く説得を試みる姿は、「常識を知らない無知」もしくは「強引」そのものに映るでしょう。しかし、この「強引さ」を欠けば、企業は過去の栄光にすがりながら、市場の変化から取り残され、緩やかに衰退していく運命を避けられません。
すべては「顧客への憑依」から始まります
では、「強引」と見なされる行動の是非を判断する基準はどこにあるのでしょうか。それは、その行動の源泉が、個人的な功名心や部門のエゴイズムではなく、「顧客の立ち位置がすぐ再現できるくらい理解し、共感し、憑依する」ことから生まれているかどうか、という一点に尽きます。
この「顧客への憑依」なくして、社内事情や過去の常識を打ち破る正当性とエネルギーは生まれません。なぜなら、顧客の解像度が低いままでは、反対意見に対して「確かにそういう側面もあるかもしれない」と安易に迎合してしまい、議論は結局、社内のパワーバランスや声の大きい者の意見に流されてしまうからです。それは「調和」という名の「現状維持」であり、思考停止に他なりません。ここが結果を出すための分水嶺です。
顧客憑依の実践例:Airbnbの初期戦略
Airbnbの共同創業者であるブライアン・チェスキーとジョー・ゲビアは、サービス開始当初、サイトの利用が伸び悩んでいました。彼らはニューヨークのリスティング(貸し出し物件)のデータを見ていて、ある共通点に気づきます。それは、物件の写真が素人っぽく、魅力に欠けることでした。当時のWebサービスの「常識」からすれば、改善策は「ユーザー向けに良い写真の撮り方ガイドを作成する」といったものだったのです。しかし、彼らは違いました。彼らはサンフランシスコからニューヨークへ飛び、自らプロ仕様のカメラを借りて、リスティングのあったホストの家を一軒一軒訪問し、無料で物件の写真を撮影して回ったのです。
この行動は、スタートアップの限られたリソースの使い方として、極めて「非効率」で「スケーラブルではない」、まさに社内(といっても当時は数人でしたが)の常識からすれば「強引」で「わがまま」な判断でした。しかし、彼らはホストという「顧客」に憑依していました。ホストが綺麗な写真を撮れない、あるいは撮る時間がないという課題を、自分自身の課題として捉えていたのです。結果として、プロが撮影した美しい写真が掲載されたリスティングは予約が2~3倍に増え、これがAirbnbの初期成長を牽引する起爆剤となりました。彼らの「強引さ」は、顧客の成功を誰よりも信じ、そのために行動した「憑依」の証だったのです。
このレベルの憑依がなければ、全ては社内事情と過去延長の常識の繰り返しになります。誰かが顧客の代弁者となり、その視点から良し悪しを判断する役割を担わなければ、組織は内向きの論理に支配され、顧客不在の意思決定を延々と繰り返すことになるのです。
「調和」がもたらす緩やかな死
顧客への憑依を欠いたまま、単に「強引さ」を避け、「調和」を優先する組織は、どのような末路を辿るのでしょうか。そこには、劇的な破綻ではなく、「緩やかな死」へと至る恐ろしい落とし穴が待っています。
アイデアの骨抜きと「最大公約数的」な凡庸さ
革新的なアイデアは、常に尖っており、誰かにとっては「異物」に映ります。顧客の特定の深いインサイトを突いた企画は、関係者が増えるほど「もっと万人受けするように」「リスクがある」「前例がない」といった意見にさらされます。ここで「調和」を重んじると、当初のアイデアの尖った部分は次々と削ぎ落とされ、誰からも強く反対されない代わりに、誰の心にも響かない、当たり障りのない「最大公約数的」なアウトプットに成り果てます。結果として、多大なリソースを投じたにもかかわらず、市場で全くインパクトを残せずに終わるプロジェクトが量産されていくのです。
意思決定の遅延と機会損失
全会一致や全員の納得感を「調和」の定義とする組織では、意思決定が著しく遅れます。市場は刻一刻と変化し、競合は次々と新しい手を打ってきます。その中で、「関係者全員の合意が取れるまで」と議論を重ねているうちに、千載一遇のビジネスチャンスは目の前を通り過ぎていきます。スピードが重要な現代において、遅い意思決定は、何もしないという最悪の意思決定と同義です。
情熱の枯渇と組織の陳腐化
最も深刻な問題は、組織文化への影響です。顧客のために本気で何かを変えたいと願う情熱的な社員が、何度も社内の分厚い壁に跳ね返されるうちに、「どうせ言っても無駄だ」「波風を立てずに、言われたことだけやっている方が楽だ」と考えるようになります。彼らの情熱の炎は消え、挑戦する文化は失われます。「強引」を貫くことができず、「わがまま」とみられた挑戦者は徐々に去っていきます。残るのは、現状維持を望む社員ばかりです。こうして組織は新陳代謝を失い、外部環境の変化に対応できない硬直化した集団へと変貌していきます。これこそが、調和を求めることの最大の罠、「緩やかな死」の正体です。
誰が「聖なる強引さ」を担うべきか
では、企業はどのようにしてこの罠を回避すればよいのでしょうか。その鍵を握るのが、CMO(最高マーケティング責任者)や執行役員といった経営層の役割です。彼らにこそ、「顧客へ憑依」し、その代弁者として社内の壁を突破する「強引さ」を発揮することが求められます。
責務は以下の三つに集約されます。
顧客の代弁者として立つこと: 経営会議の場において、常に「それは本当に顧客のためになるのか?」という問いを投げかけ、顧客の視点から全ての議論、事業戦略を評価し、修正します。
既存の秩序の破壊者となること: 部門間の利害対立や過去の常識が顧客価値の実現を阻んでいると判断した場合、時にはトップダウンでその秩序を破壊します。その際、外部コンサルタントや顧客の生の声を「外圧」として戦略的に活用することも有効な手段となります。
最終的な責任を負うこと: 「強引」に見える意思決定がもたらす結果の全責任を負う覚悟を持つことです。成功すれば、その成果を社内に浸透させ、新たな常識として定着させます。もし失敗したならば、その責任を引き受け、次の挑戦への糧とします。この覚悟なくして、真のリーダーシップは発揮できません。
私がお会いさせて頂いた結果を出し続けるリーダーは、コミュニケーションスタイルの強弱の違いはあれど、一貫して、この3つを徹底されています。そして、そのようなリーダーは、常に少数なので、多くの方々は、このようなリーダーと直接仕事をする機会がないので、おそらく特殊に見えていると思います。
様々な方々と仕事をさせて頂いて申し上げられることとして、まず、ビジネスにとって真の「調和」とは、社内の人間関係が波風立たない状態を指すのではないということです。それは、デザイナーも、エンジニアも、営業も、マーケターも、全ての社員が「顧客価値の最大化」という唯一絶対の目的に向かって、それぞれの専門性を最大限に発揮し、結果としてベクトルが揃っている状態を指します。顧客への価値を徹底するから、結果としてベクトルが揃って「調和」するのです。「調和」は成功への前提ではないのです。その理想的な状態に組織を導くために、リーダーは時に孤独な「強引さ」を貫かなければなりません。その痛みと覚悟の先にこそ、企業と顧客が共に成長する未来が待っているということを幸運にも私は学ばせて頂きました。この記事を書きました。参考になれば幸いです。
まだ会員登録されていない方へ
会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です