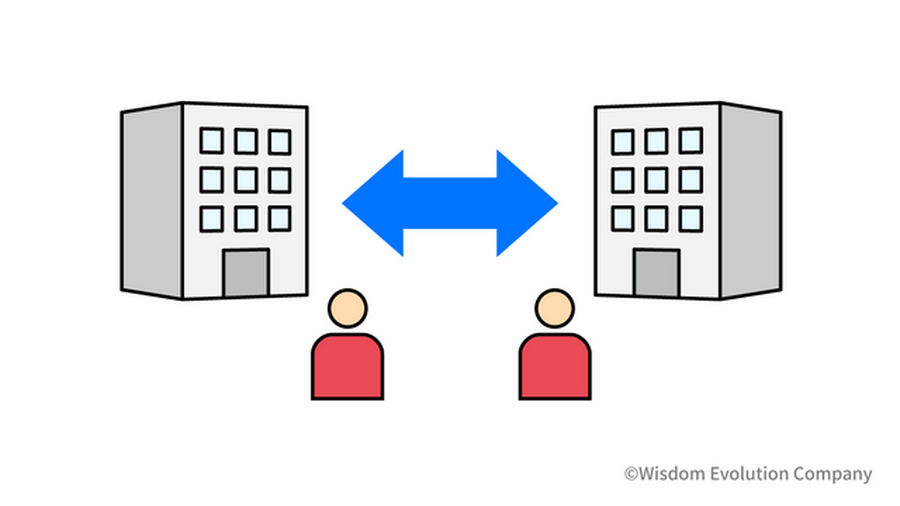
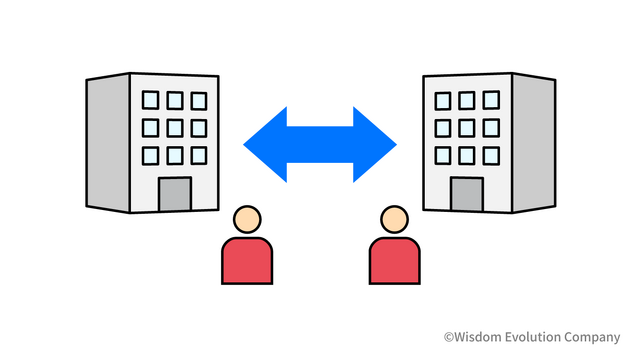
第1章:日本市場に眠る「巨大な金脈」と、それを掘り当てるための知恵
BtoBマーケティング(Business to Business Marketing)とは、一つの企業が、他の企業や組織を対象として自社の製品やサービスを販売し、長期的な関係を構築していくための、包括的かつ戦略的なマーケティング活動全般を指します。その究極の目的は、単に製品を売ることにとどまりません。顧客(クライアント)となる企業の事業内容や課題を深く理解し、製品の企画・開発から販売、そして導入後の顧客サービスに至るすべてのプロセスをコントロールすることで、顧客一社一社に対してパーソナライズされた体験と、事業の成功に貢献するという本質的な価値を実現することにあります。
経済産業省の調査によれば、日本の企業間電子商取引(BtoB-EC)の市場規模だけでも370兆円を超え、これは消費者向け(BtoC-EC)の約17倍にも上ります。これは把握できるBtoB市場全体の一部に過ぎず、オフラインの取引も含めれば、その規模は計り知れません。
しかし、日本のBtoBマーケティングは長い間、発展の途上にありました。その歴史を紐解くと、1970年代には、主に製造業者が他の企業に機械や部品を販売するための「産業マーケティング」としてその原型が注目され始めました。1980年代以降、市場のグローバル化と競争の激化に伴い、BtoCマーケティングで培われたセグメンテーション(市場細分化)、ターゲティング(狙う市場の決定)、ポジショニング(市場における自社の位置付け)といった戦略的な理論が適用される「ビジネスマーケティング」へと概念が進化します。そして現代、インターネットの普及とデジタル化の波が押し寄せ、その戦略はデータとテクノロジーを駆使する、より高度で複雑なものへと変貌を遂げ、その中で、BtoBマーケティングは、BtoCマーケティングの影響を大きく受けながらも、独自の進化を続けています。BtoBビジネスにおいて、マーケティングで成功を収めるためには、まず大前提として「BtoBはBtoCとは全く異なる」という事実を認識し、その違いを深く理解することが不可欠です。
本稿では第1章から第3章で、まずBtoBマーケティングの基本概要を解説し、BtoB市場を攻略するための「思考のOS」をインストールすることを目指します。
第1章は、すべての土台となる知識、すなわち、なぜBtoBビジネスではBtoCマーケティングでは不十分なのか、その構造的な違いと、安易な流用がもたらす失敗について、具体例を交えながら解き明かしていきます。
BtoBとBtoCを隔てるもの──6つの決定的差異
BtoBマーケティングを学ぶ最初のステップは、「BtoCとの違いを知る」ことから始まります。この違いを軽視することは、天候も海図も読まずに荒海へ漕ぎ出すことに等しく、ほとんどの場合、貴重な予算と時間を浪費し、疲弊するだけの結果に終わります。ここでは、両者のビジネスモデルを隔てる6つの決定的な違いを、一つひとつ掘り下げます。
1. 顧客(Customer):個人の「感情」と組織の「合理」が織りなす複雑な意思決定
BtoCマーケティングにおける顧客は、言うまでもなく「個人」です。購入の意思決定は、基本的にはその人一人が行います。もちろん、家族に相談することはあるかもしれませんが、最終的な判断の主導権は個人にあります。そしてその判断は、「これが欲しい」「これがあれば生活が楽しくなりそう」といった、機能的な便益だけでなく、感情や情緒といった極めて人間的な要素に大きく左右されます。一方で、BtoBマーケティングにおける顧客は「組織」です。これは単に相手が会社である、という事実だけを指すのではありません。最も重要な特徴は、購入の意思決定プロセスに、多種多様な立場と役割を持つ人々が関与するという点です。この意思決定に関わる関係者グループのことを、マーケティング用語でDMU(Decision Making Unit)と呼びます。
例えば、あるSaaS企業が、中堅製造業の「山田製作所」に新しい在庫管理システムを提案する場面を想像してみましょう。この商談には、一体何人の登場人物が関わるでしょうか。
利用者(User): 実際にシステムを日々操作する、倉庫管理担当の田中さん。最大の関心事は「操作が簡単か」「今の業務が楽になるか」です。
評価者(Influencer): システムの導入に際し、技術的な観点から評価を行う、情報システム部の高橋さん。「既存システムとの連携は可能か」「セキュリティは万全か」という専門的な視点で製品を評価します。
購買担当者(Buyer): 契約条件の交渉や価格の妥当性を判断する、購買部の鈴木課長。ミッションは「コストを抑えつつ、他よりも有利な条件で契約すること」です。
意思決定者(Decider): 最終的に導入の可否を判断し、予算の承認権限を持つ、製造部長の佐藤さん。「この投資によって、どれだけのコスト削減や生産性向上が見込めるのか」、つまりROI(投資対効果)を重視します。
承認者(Approver): 佐藤部長の決定を最終的に承認する、役員の渡辺さん。「この投資が、会社の中期経営計画やDX推進戦略とどう整合性が取れるのか」という、より大局的な視点を持っています。
このように、たった一つの製品を導入するために、関わる人々の立場、役割、そして評価基準は全く異なります。田中さん個人がどれだけ製品を気に入っても、高橋さんがセキュリティにNGを出せば進みません。佐藤部長がROIに納得しなければ、予算は付きません。BtoBマーケティングとは、これらすべての登場人物の懸念を解消し、それぞれの立場におけるメリットを提示し、組織全体の合意形成を導く、極めて高度なコミュニケーション活動なのです。個人の感情に訴えかけるだけでは、この複雑な連立方程式は決して解けません。
2. 製品・サービス(Product/Service):一過性の「モノ」と継続的な「ソリューション」
BtoC市場で取引される製品の多くは、不特定多数の消費者に向けて標準化された「モノ」です。スマートフォン、飲料、衣類など、比較的低単価で、消費者は大きなリスクを感じることなく購入を決定できます。対照的に、BtoBで提供される商材は、顧客の特定の、そして深刻な課題を解決するために提供される「ソリューション」としての性格を強く持ちます。それは単なるモノ売りではありません。顧客の業務プロセスに深く入り込み、コンサルティングを通じて最適な形を提案し、導入後も継続的なサポートを通じて価値を提供し続ける、長期的なコミットメントを前提としたサービスです。価格も数百万から数億円に及ぶことが珍しくなく、顧客にとっては経営を左右しかねない重要な投資判断となります。特に近年主流となっているSaaS(Software as a Service)ビジネスは、この「ソリューション」提供の典型です。売り切りではなく、月額や年額で利用料を支払うサブスクリプションモデルは、「一度導入したら終わり」ではなく、「顧客が価値を感じ続けている限り契約は続く」ということを意味します。これは、提供する側にとって、常に製品をアップデートし、顧客の成功を能動的に支援し続ける責任が伴うことを意味しています。
3. 関係性(Relationship):短期的な取引と長期的なパートナーシップ
前述の「ソリューション」としての性質とも関連しますが、BtoBとBtoCでは顧客との関係性の深さと長さが根本的に異なります。BtoCでは、初回の購入場面までの接点で関係がほとんど終了するケースも少なくありません。しかしBtoBでは、長期的な関係構築こそがビジネスの生命線です。その根底にあるのはビジネスパートナーとしての「信頼」です。では、BtoBにおけるビジネスパートナーとしての「信頼」とは一体何でしょうか。それは、以下の3つの要素に分解できます。
約束を守る信頼: 製品が仕様書通りの性能を発揮する、納期を遵守する、といった期待値に見合う基本的な品質提供
期待を超える信頼: 導入後に発生したトラブルに迅速かつ的確に対応する、顧客自身も気づいていないような改善点を提案するなど継続的なサポートとコンサルティング
未来を共創する信頼: 顧客の事業の成長に合わせて製品を進化させ、数年後もビジネスを支え続けてくれるという継続性への安心感
BtoBマーケティングの主要な目標は、こうした多層的な信頼関係を顧客企業と築き上げ、単なる取引相手ではなく、事業の成功に共にコミットする「パートナー」として認識されることにあります。契約書にサインをもらうことはゴールではなく、真のパートナーシップを築くためのスタートラインに立ったに過ぎないのです。
4. 価値連鎖(Value Chain):短い線と長い連鎖
BtoCにおける価値連鎖(バリューチェーン)は、比較的シンプルです。例えば、飲料メーカーが作ったジュースを、消費者が飲んで「おいしい」と感じる。企業から消費者へ、という価値提供の流れは直接的で短い線で結ばれています。ところがBtoBの世界では、この価値連鎖は長く、複雑な鎖のように連なっています。
先ほどの工作機械メーカーの例を考えてみましょう。
工作機械メーカーが、最新鋭の精密加工機を開発しました。
このメーカーは、自動車部品メーカーである「A社」にこの機械を販売します。
A社はこの機械を使って、EV(電気自動車)向けの高性能なモーター部品を製造します。
このモーター部品は、世界的な自動車メーカー「B社」に納入されます。
B社はその部品を使って、次世代のEVを生産し、最終的に消費者の手に渡ります。
消費者はそのEVに乗ることで、「安全で、静かで、環境に優しい快適な移動」という価値を享受します。
この時、工作機械メーカーが見るべきは、直接の顧客であるA社の「もっと精密な部品を作りたい」というニーズだけではありません。その先にあるB社の「より高性能なEVを作りたい」という目的、さらには最終消費者の「より良い移動体験をしたい」という便益まで、長い価値の鎖全体を見通す必要があります。この大局的な視点を持つことで初めて、「B社の次世代EV戦略には、これほどの性能を持つ部品が必要になるはずだ。そのためには、我々のこの機械がA社にとって不可欠だ」という、一段深いレベルでの価値提案が可能になるのです。
5. 価格(Price):明瞭な「定価」と、価値を証明する「見積もり」
BtoC製品の多くには、誰が見てもわかる「定価」があります。価格交渉の余地は少なく、消費者はその価格を受け入れるか否かを判断します。BtoBでは、個別見積もりが基本です。導入規模、契約期間、カスタマイズの有無、サポートのレベルなど、無数の要素を考慮して価格が決定され、交渉も当たり前のように行われます。ここで最も重要なのは、単なる価格の安さではありません。担当者が上司や経営陣を説得するために不可欠な、「この価格に見合う、あるいはそれ以上の価値(ROI)がある」という論理的な証明です。例えば、「このシステムを導入すれば、在庫管理にかかる人件費が年間500万円削減できます。システムの年間利用料は300万円ですので、差し引き200万円の利益改善に繋がり、投資は1年以内に回収可能です」といった、具体的で説得力のある数字を示すことが求められます。価格提示は、単なる値段の通知ではなく、価値を証明するプレゼンテーションなのです。
6. プロモーション(Promotion):広い「認知」と深い「信頼」の醸成
BtoCのプロモーションは、大規模なデジタルマーケティング、SNSキャンペーン、テレビCMに代表されるように、多くの潜在顧客にブランド名や製品を知ってもらう「認知度向上」が大きな目的となります。一方、BtoBのプロモーションの核は、特定の顧客層との深い「信頼関係」を構築することにあります。顧客の購買ジャーニーは、「知らない→知っている」という単純なものではありません。「自社の課題を認識する→解決策の情報収集を始める→複数の選択肢を比較検討する→専門家の意見を聞きたい→最終候補に絞り込む」といった、数ヶ月から時には数年に及ぶ長い道のりです。BtoBマーケターの役割は、この長い旅路の各段階で、顧客が必要とする最適な情報を提供し、伴走することです。例えば、課題認識の段階では課題解決のヒントとなるホワイトペーパーを、比較検討の段階では他社との違いが明確にわかる導入事例を、専門家の意見が聞きたい段階では質疑応答も可能なウェビナー(オンラインセミナー)を提供する。こうした地道な情報提供を通じて、「この会社は我々の業界や課題をよく理解している、信頼できる専門家だ」という認識を醸成していくことが、BtoBプロモーションの本質です。
BtoC思考が招く、BtoBマーケティング5つの罠
BtoC(消費者向け)ビジネスで成功したマーケティング手法を、そのままBtoB(法人向け)に持ち込んでしまい、成果が出ずに苦しむケースは少なくありません。その原因は、両者の「顧客」「購買プロセス」「求められる価値」が根本的に異なることを理解しないまま、戦術を単純適用してしまうことにあります。ここでは、よく見られる5つの罠を解説します。
1:【ターゲットの罠】「個人」と「組織」を混同する
BtoBの顧客は、個人の感情や好みだけで意思決定する「消費者」ではなく、複数の人間が合理的な基準で判断する「組織」です。この違いの無視が、最初のつまずきを生みます。
独りよがりな担当者アプローチ:
製品の利用者である現場担当者(例:倉庫担当の田中さん)個人にだけ響くような「使いやすさ」「ポップな見た目」を訴求しても、購買は決まりません。その上司である部長(意思決定者)が求める「投資対効果(ROI)のデータ」や、情報システム部門(評価者)が懸念する「セキュリティ要件」など、組織内の様々な立場の人々を納得させる論理的な情報がなければ、稟議の壁は越えられないのです。
具体性のない感情的アピール:
「貴社のビジネスを、次のステージへ。」といった、BtoCブランディングのような抽象的で感情に訴えるメッセージは、BtoBでは空振りに終わります。企業の担当者は、美辞麗句よりも「なぜこの投資が必要なのか」を社内で説明するための具体的な根拠とデータを求めています。
2:【提案内容の罠】「モノの機能」と「課題解決」を履き違える
BtoCでは製品のスペックが魅力になりますが、BtoBではその機能が「自社の事業にどう貢献するのか」という文脈が全てです。
機能自慢のスペック至上主義:
「最新CPU搭載!」「多機能!」といった機能の羅列は、BtoBの顧客にとって意味を持ちません。彼らが知りたいのは、「その機能が、自社の複雑な業務フローにどう組み込まれ、どのような課題を解決するのか」という全体像(ソリューション)です。導入プロセスやサポート体制といった現実的な側面を無視した機能自慢は、「この人たちは我々の現場を分かっていない」という不信感につながります。
「顧客の顧客」への想像力欠如:
提案の視点が、直接の取引先で止まってしまうのも典型的な失敗です。例えば、自動車部品メーカー(顧客)に工作機械を売る場合、「この機械は精度が15%向上します」だけでは不十分です。「この機械を使えば、貴社の大口取引先である大手自動車メーカーが要求する次世代EVの品質基準をクリアでき、戦略的パートナーになれます」と、顧客のビジネスの成功、つまり「顧客の顧客」まで見据えた提案ができて初めて、単なる売り込みから事業貢献への昇華が起こります。
3:【時間軸の罠】「短期決戦」と「長期的関係」を誤解する
BtoCの短期的なキャンペーン思考は、検討期間が長く、継続的な関係性が重要なBtoBでは通用しません。
キャンペーンで燃え尽きる「打ち上げ花火」施策:
BtoCの「お試しキャンペーン」のように、四半期の目標達成のためにWeb広告などを集中投下し、多数のリード(見込み客)を獲得したとします。しかし、検討期間が数ヶ月~1年以上に及ぶBtoBでは、その後の継続的な情報提供や関係構築(リードナーチャリング)の仕組みがなければ、獲得したリードは放置され、忘れ去られてしまいます。それは、広大な畑に一度だけ種を撒き、水もやらずに収穫を待つようなものです。
4:【価格提示の罠】「値札」と「投資価値」を混同する
価格の伝え方は、BtoCとBtoBで決定的に異なります。BtoCの透明性が、BtoBでは逆効果になることがあります。
文脈なき「料金プラン」の陳列:
Webサイトにいきなり詳細な料金プランを掲載すると、製品の価値を十分に理解していない担当者は「月額50万円」といった数字だけを見て、「高い」と判断し離脱してしまいます。BtoBにおける価格は、「この投資によって年間800万円のコストが削減できる」といった価値(ROI)と比較されて初めて意味を持ちます。価値の物語を伝える前に価格だけを見せるのは、対話の機会を自ら放棄する行為です。
5:【コミュニケーションの罠】「好感度」と「信頼性」を取り違える
BtoBで醸成すべきは、友人に対する「親近感」ではなく、専門家に対する「信頼感」です。
「バズ」を狙うエンタメコンテンツ:
業務用の会計ソフト企業が、業務と全く関係のない面白いネコの動画をSNSに投稿しても、それを見て笑う視聴者の中に経理部長やCFOはほとんどいません。BtoBのプロモーションで求められるのは、課題解決に貢献する専門性の高い情報です。エンタメコンテンツは、ビジネスに繋がらない注目を集めるだけでなく、「この会社は我々のビジネスの深刻さを理解していない」と専門家としてのブランドイメージを毀損するリスクさえあります。
インセンティブで釣る「偽りの見込み客」:
「Amazonギフト券5000円分プレゼント!」といったインセンティブでリードの「数」を追い求めると、製品ではなく景品に興味がある「偽りの見込み客」ばかりが集まります。マーケティング部門は目標達成に満足するかもしれませんが、質の低いリード対応に追われる営業部門は疲弊し、「マーケティングからのリードは全く役に立たない」という部門間の深刻な対立を引き起こす典型的な失敗です。
まとめ
第1章は、BtoBとBtoCの構造的な違い、そしてBtoBにとって、BtoCマーケティングが必ずしも役に立たない、また、安易な模倣がもたらす典型的な罠について解説しました。このBtoB特有の構造を深く理解し、その上で最適化された戦略を採用することが、成功への唯一の道です。しかし、このようなBtoBとそのマーケティングに関する知識不足だけでなく、部門間の連携不足や短期的なKPIの追求といった、より根深い組織的な課題が存在することも少なくありません。
次からは、これらの違いと複雑性を乗り越え、BtoBビジネスを成功に導くために、先人たちが築き上げてきた4つの強力な戦略思想(流派)を、具体的な企業の事例と共に、その実践方法に至るまで詳しく解説します。
第2章:BtoBマーケティングの「型」を知る
第1章では、BtoBマーケティングがBtoCとは根本的に異なる生態系を持つこと、そしてBtoCの常識で挑むことがいかに危険であるかを、6つの構造的差異と6つの罠を通じて解説しました。BtoBというビジネスの、複雑で、合理的で、そして長期的な関係性が求められる特異な性質をご理解いただけたかと思います。では、その複雑怪奇にも見えるBtoB市場を、具体的にどうすれば攻略できるのでしょうか。幸いなことに、私たちには先人たちの知恵の結晶があります。BtoBマーケティングは、BtoC分野を中心に発展してきたデジタルマーケティングやデータドリブンマーケティングといった多様な手法を貪欲に取り込みながら、独自の進化を遂げてきました。その試行錯誤の中で、特に有効な戦略思想として確立されてきたのが、4つの強力な「流派」です。
これらは単なる戦術の寄せ集めではありません。それぞれが明確な哲学を持ち、どのような顧客に、どのような価値を、どのような組織体制で届けるべきかという、事業の根幹に関わる「型」を示してくれます。今回は、BtoBビジネスを力強く成長軌道に乗せる4つのエンジン、すなわち「オーケストレーター型」「THE MODEL型」「ABM型」「PLG型」という4つの流派を一つひとつ、その背景思想から具体的な成功事例、そして実践の勘所まで、徹底的に掘り下げて解説していきます。
BtoBマーケティング 4つの戦略思想(流派)
ここで紹介する4つの流派は、どれか一つを選べば他は不要、というものではありません。むしろ、会社の成長フェーズや事業の特性に応じて、メインの思想を据えつつ、他の流派の要素を巧みに取り入れていくハイブリッドなアプローチが現実的です。まずは、それぞれの「型」が持つ思想と強みを深く理解することから始めましょう。
1.【オーケストレーター型】:全部門を束ね、最高の顧客体験を奏でる
これは、マーケティング部門が単なるリード獲得や広告宣伝といった限定的な役割を担うのではなく、事業戦略の中枢に立ち、製品開発、営業、カスタマーサクセス(CS)といった全部門を束ねる「指揮者(オーケストレーター)」の役割を果たすべきだという、BtoBマーケティングの一つの究極的な理想形です。
壮大なオーケストラを想像してみてください。営業部門には、卓越した技術を持つバイオリン奏者がいます。開発部門には、深みのある音色を奏でるチェロ奏者がいます。そして、顧客を丁寧に支えるカスタマーサクセス部門には、安定した音で全体を包み込む管楽器奏者たちがいます。彼ら一人ひとりが最高の演奏家であっても、それぞれが思い思いに音を奏でていては、それは美しい音楽ではなく、ただの騒音になってしまいます。
ここに、指揮者としてのマーケティングが登場します。指揮者は、「顧客」という名の難解な楽譜を、誰よりも深く読み解き、「我々が目指すのは、このような感動的な顧客体験という名の音楽なのだ」という明確なビジョンを掲げます。そして、各パートに適切な指示を出し、全体の調和を図り、最高の演奏を引き出す。これがオーケストレーター型の本質的な役割です。
背景と提唱者: この思想の源流は、「現代経営学の父」と称されるピーター・ドラッカーが述べた「企業の機能はマーケティングとイノベーションだけである」という有名な言葉にあります。つまり、顧客を理解し、価値を創造すること(マーケティング)こそが、企業の存在意義そのものであるという考え方です。現代においてこの思想が再び注目される背景には、顧客の購買行動の劇的な変化があります。米国の調査会社CEB(現ガートナー社)の有名な調査によれば、BtoBの顧客は、営業担当者に接触するまでに、購買プロセスの約6割を独力で完了させていると言われています。Webサイト、比較サイト、SNS、ウェビナーなど、オンライン上での情報収集が当たり前になった今、顧客との最初の接点から検討の大部分を担うのは、もはや営業ではなくマーケティング部門なのです。顧客との接点の全体像を最も深く理解しているマーケティング部門こそが、事業全体の舵取りをすべきだ、という必然性がここから生まれています。
具体事例:
キーエンス: 「CMO(最高マーケティング責任者)」という役職が表立って語られることは少ないですが、この会社の事業構造そのものが、まさにオーケストレーター型の思想を体現しています。彼らは「世界初・業界初」の革新的な製品を生み出し続ける開発力で知られますが、その力の源泉は、営業担当者が顧客の現場から直接吸い上げてくる「顧客自身も言葉にできていない潜在的なニーズ」という、膨大かつ質の高いマーケティングデータにあります。その生々しいデータが開発部門にフィードバックされ、顧客の課題を根源から解決する製品が生まれるのです。そして営業は、その製品が顧客のビジネスにどれほどの価値(ROI)をもたらすかを、コンサルタントのように論理的に提案します。顧客ニーズの把握(マーケティング)が、開発から営業まで全ての活動の起点となり、事業全体が完璧なハーモニーを奏でているのです。
IBM: グローバルITの巨人であるIBMも、この思想を実践する企業です。「THINK」というブランドメッセージのもと、単なる製品販売にとどまらず、コンサルティング、システム構築、基礎研究といった多岐にわたる事業を、一貫した世界観と顧客体験のもとで提供しています。各事業部がバラバラに動くのではなく、「企業のデジタルトランスフォーメーションを根源から支えるパートナーである」という大きな指揮棒のもとで、それぞれの専門性を発揮し、壮大な交響曲を奏でています。
実現の鍵:
しかし、このモデルは理想形であると同時に、実現が極めて難しい「諸刃の剣」でもあります。なぜなら、この役割はCMO個人の超人的な能力に依存しがちだからです。事業全体を俯瞰し、各部門の利害を調整し、経営の意思決定に深く関与できる人物は、市場に滅多にいません。結果として、CMOが短期で交代し、組織が混乱に陥るケースも後を絶ちません。だからこそ、多くの成功事例で見られる現実的な解は、CEO自身が事実上のCMOとして、この指揮者の役割を担うという形です。部門間の利害や文化の違いといった根深い壁を最終的に壊せるのは、全社に対する視点と絶対的な権限を持つCEOしかいないからです。あるいは、近年注目されるCRO(Chief Revenue Officer/最高収益責任者)のように、マーケティング、営業、CSの全部門の売上と利益に責任を持つ役職を置き、実質的な指揮者とするアプローチも有効です。
2.【THE MODEL(ザ・モデル)型】:再現性ある成長を実現する工場
これは、世界的なSaaS企業であるセールスフォース社(現セールスフォース・ジャパン)が、自社の急成長を支えるために構築し、特に日本のSaaS業界に絶大な影響を与えた考え方です。マーケティング、インサイドセールス、営業(フィールドセールス)、カスタマーサクセスという4つの部門が連携し、顧客獲得から契約後の成功までを分業する、いわば「顧客創出の工場モデル」です。工場の製造ラインを思い浮かべてください。各工程が専門特化し、ベルトコンベアで製品が流れていきます。
マーケティング(材料調達): 展示会やWeb広告、コンテンツマーケティングなどを通じて、「質の良い材料」となる見込み客(リード)を大量に集めてくるのが役割です。KPIはMQL(Marketing Qualified Lead)の数と質になります。
インサイドセールス(検品・加工): 集められた材料(リード)に対し、電話やメールでアプローチし、顧客の課題やニーズ、予算、導入時期などをヒアリング(検品)します。そして、確度が高いと判断した案件だけを「商談」という半製品に加工し、次の工程に渡します。KPIはSQL(Sales Qualified Lead)への転換率や商談化数です。
営業/フィールドセールス(組立): インサイドセールスから渡された半製品(商談)を、対面やオンラインでの提案を通じて「最終製品」、すなわち「契約」に組み立てるのが役割です。提案活動に集中できるため、生産性が飛躍的に向上します。KPIは受注率や受注額です。
カスタマーサクセス(品質保証・メンテナンス): 完成した製品(契約後の顧客)が、お客様の元で「長く価値を発揮し続けられるようにメンテナンス(活用支援)」する重要な役割を担います。単なる問い合わせ対応(カスタマーサポート)やカスタマーサービスとは異なり、能動的に顧客の成功を支援します。KPIは契約更新率、アップセル/クロスセル額、そして顧客ロイヤルティを示すNPS(Net Promoter Score)などです。
このモデルの最大の特徴は、各工程間の連携がSFA: Sales Force Automation (セールス・フォース・オートメーション)、CRM: Customer Relationship Management (カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)、MA: Marketing Automation (マーケティング・オートメーション)といったツールを通じて数値で徹底的に管理される点です。「リードから商談への転換率が低い」「商談から受注までの期間が長い」といったボトルネックがデータで可視化されるため、常に改善を加え続けることが可能です。
背景と提唱者: SaaS黎明期、人力の営業に頼るだけでは、爆発的な事業のスケールは望めませんでした。そこで、再現性高く、効率的に成長するための「仕組み」として、セールスフォース社が生み出したのがこのモデルです。日本では、同社の日本法人で常務執行役員などを務めた福田康隆氏の著書『THE MODEL(ザ・モデル)』によって、分業ではなく共業として広く知られるようになり、多くのSaaS企業の成長バイブルとなりました。
カスタマーサクセスの真の役割: このモデルにおいて、特に強調したいのがカスタマーサクセスの重要性です。彼らは単なる解約防止を担当するコストセンターではありません。顧客の成功を能動的に支援し、満足度を高めることで、より上位のプランへのアップグレードや、別製品の追加契約(クロスセル)に繋げ、LTVを最大化する「良い売上を生み出すプロフィットセンター」としての役割を担っています。
具体事例:
セールスフォース・ジャパン: まさにこのモデルの元祖であり、最も洗練された形で実践している企業です。大規模イベント「Dreamforce」や的確なWeb広告で膨大な数のリードを獲得し、高度に専門化されたインサイドセールス部隊が質の高い商談を創出。精鋭の営業担当者がクロージングに集中することで、組織全体として圧倒的な生産性を実現しています。
Sansan / SmartHR / freee: 日本を代表するSaaS企業は、その多くがこのTHE MODELを自社流にアレンジして導入し、急成長を遂げました。例えば、法人向け名刺管理サービスで知られるSansanは、テレビCMなどで幅広く認知を獲得し(マーケティング)、獲得したリードに対してインサイドセールスがアプローチして商談を設定。営業が訪問して契約を獲得し、カスタマーサクセスが導入後の活用を徹底的に支援することで、高い継続率を誇っています。この仕組みがあったからこそ、彼らは日本のビジネスシーンに名刺管理という新しい文化を定着させることができたのです。
3.【ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)型】:個別集中の戦略的な一本釣り
ABMは、不特定多数に網を投げる「投網漁」ではなく、最初から「この大物を釣る」と決めて狙いを定める「一本釣りの名人漁師」のような、極めて戦略的なマーケティング手法です。自社のビジネスにとって最も価値の高い、理想的な優良企業(ターゲットアカウント)を数十~数百社リストアップし、その特定の企業群を「一つの市場」と見立てて、組織の全リソースを集中投下します。マーケティング部門と営業部門が一体となり、「トヨタ自動車攻略チーム」「NTTデータ攻略チーム」といった、特定の企業を攻略するためだけの特別チームを組むようなイメージです。「皆様へ」という画一的なメッセージではなく、「トヨタ自動車の〇〇部長様へ。御社のサプライチェーンにおける△△という課題は、弊社の□□というソリューションで、このように解決できます。なぜなら、競合のホンダ様では既に同様の課題を解決した実績があるからです」といった、完全に個別最適化された、リサーチに基づいた鋭いアプローチを行います。
ABMの実践ステップ:
ターゲットアカウントの選定(Identify): 自社の既存顧客データを分析し、最もLTVが高い企業の共通項(業種、規模、地域など)を抽出して、理想的な顧客像(ICP:Ideal Customer Profile)を定義。これに基づきターゲット企業リストを作成します。
アカウント内の主要人物の特定(Expand): 選定した企業内で、意思決定に関わるDMU(利用者、評価者、意思決定者など)は誰なのかを、組織図や人事情報、SNSなどを駆使して徹底的にリサーチします。
個別メッセージの作成(Engage): リサーチした企業や個人の課題に深く寄り添った、パーソナライズされたメッセージやコンテンツを作成します。
複数チャネルでの展開(Advocate): 作成したメッセージを、ターゲット企業の担当者だけに表示されるWeb広告、経営層向けの特別セミナー、営業担当者からの個別メールなど、複数のチャネルを組み合わせて、多角的かつ集中的に届けます。
背景と提唱者:
特に、顧客となりうる企業がごく少数に限られるエンタープライズ向けのビジネスにおいて、「質の低いリードをいくら大量に集めても、営業のリソースを無駄にするだけだ」という強い課題意識から生まれました。2000年代初頭に米国のITSMA(ITサービスマーケティング協会)が提唱したとされています。
具体事例:
Oracle / SAP: 大手企業向けの基幹システム(ERP)などを販売する外資系ITベンダーは、典型的なABMの実践者です。彼らはターゲットとする業界(例:製造業、金融業)や、その業界のトップ企業を明確に定めています。そして、その企業の経営層が読むであろう日本経済新聞や業界専門誌に広告を掲載したり、CxO(最高〇〇責任者)向けのクローズドなセミナーを開催したり、営業担当者が長年かけて経営幹部とのリレーションを構築したりと、あらゆる手段を組み合わせて、「あなた(の会社)のためだけのソリューションです」という、特別で説得力のあるメッセージを届け続けています。
戦略コンサルティングファーム: マッキンゼー・アンド・カンパニーやボストン・コンサルティング・グループといった企業も、ABMの思想で動いています。彼らは不特定多数に向けた広告を打ちませんが、ターゲット企業の経営課題に深く切り込んだ調査レポート(例:「日本の製造業がDXで生き残るための5つの処方箋」)を公開したり、経営層が集まるカンファレンスで示唆に富んだ講演を行ったりすることで、「我々こそが、あなたの会社の最も困難な課題を解決できる唯一無二のパートナーである」という、圧倒的な専門性と信頼性を的確にアピールしているのです。
4.【PLG(プロダクト・レッド・グロース)型】:製品自身の最高の体験が、最高の営業となる
PLGは、「優れた製品(プロダクト)そのものが、ユーザーを惹きつけ、顧客を増やし、事業を成長(Growth)させていく」という、プロダクトを全ての活動の起点に据えた成長戦略です。これは、デパートの食品売り場で行われる「試食販売」の考え方に、非常に似ています。
従来の営業(セールス・レッド・グロース)が、「この新製品のソーセージは、A社の豚肉を使っていて、B社のスパイスで味付けされており、本当に美味しいですよ!」と営業マンが熱心に説明するモデルだとすれば、PLGは、「能書きはいいから、まず一口どうぞ」と、実際に製品を使ってもらう(無料トライアルやフリーミアムプラン)ことから始めます。その価値に心から納得したユーザーが、自然と「これをください」と有料プランに移行し、さらには同僚に「これ、すごく便利だよ」と勧めてくれる。製品そのものが、24時間365日働く、最強の営業マン兼マーケターになるモデルです。
PLG成功の鍵:
Time to Value(価値実感までの時間)の短縮: ユーザーが登録してから、製品の価値を実感するまでの時間をいかに短くできるかが生命線です。複雑な設定なしに、直感的に使えるUI/UXが不可欠です。
Aha! Moment(アハ体験)の設計: ユーザーが「なるほど、これはすごい!」「これなしでは仕事ができない!」と、製品の価値に心から開眼する瞬間(アハ体験)を設計し、そこへスムーズに導く仕掛けが重要です。例えば、チャットツールなら「チームメンバー10人と100件のメッセージをやり取りする」、Web会議ツールなら「初めての会議をノイズなく完了させる」といった瞬間です。
バイラル(口コミ)の仕組み: ユーザーが他のユーザーを招待したくなるような機能(例:共同編集機能、招待ボーナスなど)を製品に組み込むことで、自然な形で利用者が増えていく仕組みを構築します。
背景と提唱者:
SlackやFigma、Dropboxのように、まず企業のIT部門の許可を得ずとも、現場の従業員が個人で無料版を使い始め、その圧倒的な便利さが口コミでチームや組織全体に広まっていき、最終的に会社として正式に有料版を導入する、という「ボトムアップ型」SaaSの台頭が背景にあります。この新しい成長モデルを、米国のベンチャーキャピタルであるOpenView Venture PartnersがPLGと名付け、体系化したことで広く知られるようになりました。
PLGと営業の共存:
PLGは「営業が不要」という意味では決してありません。セルフサービスで満足する中小企業の顧客層と、より高度なセキュリティやサポート、大規模な導入支援を必要とする大企業の顧客層では、求められる対応が異なります。後者に対しては、製品の利用データを基に、「この企業は有料プランに移行する可能性が高い」と判断し、専門の営業チームがアプローチする(プロダクト・レッド・セールス)といった、ハイブリッドなモデルが主流になりつつあります。
具体事例:
Slack / Zoom:PLGの教科書的な事例です。特にZoomは、コロナ禍で多くの人々が無料版を使い始め、その手軽さと接続の安定性から、あっという間にビジネスシーンのスタンダードになりました。多くの企業が、従業員が既に使い慣れているという理由で、セキュリティや管理機能が強化された有料のビジネスプランを契約しました。無料版で広く深く体験された価値が、企業が有料プランを契約する強力な、そしてほとんど不可逆的な動機付けになったのです。
Chatwork: 日本におけるPLGの成功事例です。メールや電話に代わるビジネスコミュニケーションツールとして、無料で簡単に始められる手軽さが、特に中小企業を中心に受け入れられました。ITに詳しくない人でも直感的に使えるシンプルな設計で、まずは一部のチームで導入され、その便利さが口コミで社内に伝播していくことで、日本のビジネスシーンに広く浸透していきました。
まとめ
第2章では、BtoBマーケティングという複雑な航海を乗り切るための、信頼できる4つの「型」、すなわちオーケストレーター型、THE MODEL型、ABM型、PLG型を詳しく解説しました。それぞれに異なる哲学、強み、そして適用すべきビジネスの状況があることをご理解いただけたかと思います。
オーケストレーター型は、全部門を束ねる理想の「思想」。
THE MODEL型は、再現性ある成長を実現する「仕組み」。
ABM型は、高単価市場を攻略する「集中戦略」。
PLG型は、優れた製品で市場を席巻する「プロダクト戦略」。
しかし、「では、結局のところ自社はどれを選べばいいのか?」「これらをどう組み合わせれば、相乗効果が生まれるのか?」という、最も実践的な疑問が湧いてきているはずです。また、これらの強力な「型」を導入しようとしても、多くの企業が組織の壁によって、その効果を十分に発揮できずにいるという厳しい現実もあります。
この後は、いよいよこの記事のクライマックスとして、これらの戦略を自社の状況に合わせて選び、効果的に組み合わせるための実践的なフレームワークを解説します。さらに、多くの企業が直面するBtoBマーケティングを阻む根深い組織的な壁とその具体的な克服法、そしてAI時代を見据えた未来の潮流にまで踏み込み、BtoBマーケティングという壮大なテーマの議論を締めくくります。
第3章:戦略を「実践」と「進化」へ
第1章でBtoBマーケティングがBtoCとは全く異なる論理で動く世界であることを解き明かし、第2章でその複雑な世界を航海するための4つの強力な戦略思想(オーケストレーター、THE MODEL、ABM、PLG)という羅針盤を手に入れました。これからは、これらの戦略を単なる知識、すなわち「机上の空論」で終わらせず、自社の血肉として事業を成長させるための、具体的な実践論を紹介します。具体的には、まず「どの戦略を選ぶべきか」という問いに答えるための判断軸を示し、次に各戦略の相乗効果を最大化する組み合わせの妙を探ります。そして、最も重要とも言える、多くの企業が直面する組織的な壁をいかに乗り越えるかという処方箋を提示します。
自社に最適な「型」の見つけ方 ~戦略選択のフレームワーク~
4つの流派を前に「どれも魅力的だが、自社はどこから手をつければいいのか?」と悩むのは当然のプロセスです。ここでは、自社の状況を客観的に分析し、最適な戦略の初期設定を行うための、シンプルかつ強力なフレームワークを紹介します。
1. 基本のフレームワーク:「顧客単価 × ターゲット顧客数」
すべての基本となるのが、この2つの軸で構成されるマトリクスです。自社の製品・サービスが、一社あたりから得られる平均的な年間売上(ACV:Annual Contract Value)と、顧客となりうる企業の総数を、このマトリクス上にプロットしてみてください。
【右下の象限:低単価 × 顧客数が多い】→ まずは「THE MODEL型」か「PLG型」から
この領域のビジネス(例:月額数千円~数万円で利用できるSaaS、消耗品など)で成功するためには、効率性と再現性が絶対的な鍵となります。一社一社に手厚い営業をかけることは採算が合わないため、仕組みで市場を攻略する必要があります。
プロダクト自体がシンプルで、ユーザーが自力で価値を体験できるのであれば、PLGが極めて有効な選択肢となります。製品そのものが営業マンとなり、口コミで広がっていくのを後押しする戦略です。
一方で、ある程度の説明や導入支援が必要な製品であれば、THE MODELが軸になります。マーケティングで広くリードを獲得し、インサイドセールスが効率的に顧客を育成・選別する工場モデルを構築することで、スケーラブルな成長を目指します。
【左上の象限:高単価 × 顧客数が少ない】→ 間違いなく「ABM型」
この領域(例:大企業向けの基幹システム、コンサルティング、大型機械など)では、顧客一社あたりの価値が極めて高いため、リソースの集中投下が最も効果的です。数少ないターゲット企業を明確に定め、その一社を落とすために、マーケティングと営業が総力戦で挑むABMが、唯一にして最適な戦略と言えます。
「オーケストレーター型」の位置づけ
では、「オーケストレーター型」はどこへ行ったのでしょうか? これは、上記のマトリクスで選べるような特定の戦術ではありません。むしろ、THE MODEL、PLG、ABMといった全ての実行エンジンを動かすための、事業全体の理想的な「戦略・思想」そのものです。どの戦術を選ぶにせよ、部門間の連携と顧客中心主義というオーケストレーターの思想がなければ、戦略は形骸化してしまいます。その役割をCMOが担うのかCEOが担うのかCROが担うのかは明確に決めておかなければなりません。
2. 追加の判断軸による解像度向上
上記の基本フレームワークに、以下の2つの軸を加えることで、戦略選択の解像度はさらに高まります。
軸③:製品・サービスの複雑性
Self-service(自己解決)可能か? この問いへの答えが「Yes」ならば、PLGのポテンシャルは非常に高いと言えます。ユーザーがマニュアルを読んだり、少し触ったりするだけで、「なるほど、こう使えばいいのか!」と価値を実感できる製品は、PLGの成功要件を満たしています。
導入コンサルティングが必須か? 逆に、顧客の既存システムとの連携や、複雑な業務フローに合わせた詳細な設定、担当者へのトレーニングなど、専門家による手厚い導入支援が不可欠な製品の場合、PLGは機能しにくくなります。この場合は、THE MODELやABMといった、人の介在を前提としたアプローチが必須となります。
軸④:市場と組織の成熟度
企業の成長フェーズに応じた段階的移行: 多くの成功企業は、単一の戦略に固執するのではなく、成長フェーズに応じて戦略を柔軟に進化させています。
成長フェーズ1:ゼロイチ 0→1・創業期(シード期)
まずは優れた製品を作ることに集中し、PLG的なアプローチで熱心な初期ユーザーを獲得し、PMF(プロダクトマーケットフィット)を達成することを目指します。
成長フェーズ2:1→10期(利益性の確立まで)・成長期(シリーズA~B)
ユーザー基盤が拡大し、より組織的な販売体制が必要になった段階でTHE MODELを導入。再現性のある成長エンジンを構築し、売上伸長から営業利益が生まれ利益性が確立されるまで事業をスケールさせます。
成長フェーズ3:10→1000期(積極投資から売上と利益の最大化)・成熟期(上場後など)
売上伸長に伴って安定した利益が生まれる事業基盤の上で、さらなる成長を目指してエンタープライズ市場を開拓するために、積極投資し、専門のABMチームを立ち上げます。このような段階的な戦略移行は、リソースが限られるスタートアップにとって非常に現実的なロードマップです。
「4つの流派」の組み合わせによるシナジー最大化
単一の戦略を実行するだけでも大きな成果は期待できますが、真の競争優位性は、これらの戦略を巧みに組み合わせ、相乗効果を生み出すことで生まれます。
PLG × THE MODEL:『プロダクトによる“試食”』と『組織的な“おもてなし”』の究極の融合
これは現代のSaaS企業における王道の組み合わせです。まず、PLG戦略によって、無料プランやトライアルでプロダクトの「試食」を広く促します。そして、バックエンドではMA(マーケティングオートメーション)ツールがユーザーの行動を常に監視しています。
例えば、「特定の有料機能を3回クリックした」「価格ページを5回閲覧した」「チームメンバーを10人招待した」といった、購入意欲の高まりを示す行動(シグナル)を検知すると、そのユーザー情報は自動的にスコアリングされます。
そして、スコアが一定の閾値を超えた有望なユーザー(特に企業ドメインで登録しているユーザー)のリストが、THE MODELのインサイドセールスチームに自動で通知されます。通知を受けたインサイドセールスは、「〇〇様、製品をご利用いただきありがとうございます。△△の機能でご不明な点はございませんか?もしよろしければ、さらに高度な活用法をご案内します」と、完璧なタイミングでアプローチします。
これは、相手がすでに製品のファンである可能性が高く、極めて温度感の高い商談から始められるため、成約率が飛躍的に向上します。プロダクトの力(PLG)と人の力(THE MODEL)が互いの長所を最大限に引き出す、非常に強力なモデルです。
ABM × PLG:『データに基づいた科学的な一本釣り』
伝統的なABMが、業界動向や企業情報といった外部情報からターゲットを選定するのに対し、この組み合わせはPLGで得られた内部の製品利用データを武器にします。
ABMチームがターゲットアカウントリストに載せている「トヨタ自動車」を例に考えてみましょう。ある日、分析ツールが「@toyota.co.jp」ドメインからの無料版登録者数が、この1週間で30人から150人に急増していることを検知します。これは、社内の誰かが使い始め、その便利さが口コミで部署内に一気に広まっている強力な証拠です。
このデータという「確証」を得たABMチームは、即座に行動を開始します。営業担当者は、その部署のキーパーソンに「御社の〇〇部では、既に150名の方に弊社のツールをご活用いただき、ご好評をいただいております。ぜひ一度、全社的な導入による効果について、情報システム部門のご担当者様とお話しさせて頂けませんでしょうか」と、極めて説得力の高いアプローチが可能になります。勘と経験に頼りがちだったABMを、データドリブンで科学的なアプローチに進化させることができるのです。
BtoBマーケティングを阻む壁と、その克服
どれだけ優れた戦略を描いても、それを実行する組織に問題があれば、絵に描いた餅に終わります。ここでは、多くの企業が直面する課題と、それを乗り越えるための解決策を提示します。
1. 組織の壁:部門間の分断(サイロ化)とKPIの不整合
課題: マーケティング部門はリードの「数」をKPIにしているため、質を度外視してとにかく多くのリストを集めようとします。営業部門は「受注額」がKPIなので、質の低いリードには見向きもせず、「マーケは使えない」と不満を募らせます。カスタマーサクセスは「更新率」がKPIですが、営業が無理な値引きや過剰な期待をさせて契約した顧客の対応に追われ、疲弊しています。このように、各部門が自部門のKPI達成のみを追求した結果、組織はバラバラになり、顧客視点での一貫した体験は完全に失われます。
解決策: この根深いサイロ化を打ち破るには、強力なリーダーシップが不可欠です。オーケストレーター型の思想に基づき、CEOやCROが旗振り役となり、部門個別ではなく、事業全体の成功に繋がる共通の目標(最終的にはLTVや利益)をトップダウンで設定する必要があります。そして、マーケティングが獲得したリードが、最終的にどれだけ優良顧客(LTVの高い顧客)に繋がったかを可視化し、その成果をマーケティングの評価にも反映させるなど、部門を横断した評価制度の改革も必要です。
2. 財務の壁:「悪い売上」の発生リスクとLTV/CAC経営の徹底
課題: 長期展望なく目先の売上目標を達成するために、営業担当者が将来の解約リスクが高い顧客と無理に契約したり、過度な値引きに応じたりします。短期的には売上が立つため、問題が見えにくく、「売上は順調に伸びている」と経営陣が誤った判断を下しがちです。しかし水面下では、高い顧客獲得コスト(CAC)を回収できないまま解約が相次ぎ、会社の利益はじわじわと蝕まれていきます。この継続性な利益を生み出さない一過性の「悪い売上」は、企業にとって麻薬のようなものです。
解決策: BtoB、特にSaaSビジネスの経営は、LTVとCACのユニットエコノミクスを羅針盤としなければなりません。まず、LTVは売上ベースではなく、必ず粗利や営業利益ベースで算出することが重要です。そして、一般的に健全性の目安とされる「LTV ÷ CAC > 3」という基準を常に監視し、この比率を上回る事業構造を維持・改善するための意思決定(価格改定、営業プロセスの見直し、解約率低下施策など)を、データに基づいて行い続ける必要があります。
3. 顧客理解の壁:「マス思考」の弊害と、N1分析による共感の醸成
課題: アンケート調査の結果やウェブサイトのアクセス解析データを見て、「当社の顧客の平均像は、従業員500名規模の製造業で、課題はコスト削減」といった、最大公約数的な顧客像を描いて満足してしまいます。この「マス思考」からは、顧客の心に響くメッセージは生まれません。また、現場の声を聞こうとしても、「価格を安くしてほしい」「この機能を追加してほしい」といった表面的な要望に終始し、その言葉の裏にある顧客の本当の悩みや、業務上の構造的な課題を深掘りできません。
解決策: この壁を越えるには、たった一人の顧客(N=1)を、そのビジネスや人生の背景まで含めて、徹底的に深く理解する「N1分析」のようなアプローチが極めて有効です。一人の顧客に数時間にわたるインタビューを行い、彼らがどのような課題に悩み、どのような情報収集を経て、なぜ最終的に自社製品を選んだのか、そして導入後にどのように成功(あるいは失敗)したのかを、ストーリーとして描き出します。そして、その一人の顧客の生々しい物語を、社内の共通言語・共通資産として共有することで、組織全体に「我々の顧客とは、こういうことで悩んでいる、こういう人たちなんだ」という深い共感と理解が生まれるのです。
4. 経営の壁:顧客起点の視点欠如と、CRO(最高収益責任者)の必要性
課題: 多くの企業の役員会議で交わされるのは、売上や利益といった財務諸表上の数字の話ばかりです。「あなたの会社の役員会議で、先月契約した『〇〇社』の担当者の顔と名前が、何人出てきますか?」この問いに答えられないとしたら、それは経営と現場の顧客理解が乖離している証拠です。経営層が顧客の心理や行動を、議論の対象として具体的に管理できていないことが、前述したすべての問題の根源にあると言っても過言ではありません。
解決策: この最も根深い壁を打ち破るために、近年注目されているのがCRO(Chief Revenue Officer)という役職です。CROは、マーケティング(リード創出)、営業(契約獲得)、カスタマーサクセス(LTV最大化)という、企業の収益(Revenue)を生み出す一連のプロセス全てに責任を持つ司令塔です。CROを設置することで、部門間の対立を乗り越え、経営レベルで一貫した顧客戦略と収益戦略を描き、実行することが可能になります。
まとめ
ここまで、3章に渡ってBtoBマーケティングの基本とその実践論について紹介してきました。要約するならば、BtoCマーケティングは、「個人の感情に訴えかけ、比較的短期間で「購入」というゴールを目指す華やかな短距離走であるのに対し、BtoBマーケティングは、組織の「合理」に訴えかけ、長期的な「信頼関係」を設計・構築しながら、顧客の「ビジネス上の成功」という、遥か先にあるゴールを共に目指す、忍耐と知性が求められるビジネスパートナーとしての長距離走」です。
解説してきた4つの戦略思想やその組み合わせは、この長く険しい道のりを、科学的に、そして再現性高く走り抜くための強力な武器となります。そのために重要なのは、組織の壁を越える覚悟です。部門間のサイロを壊し、短期的な売上という「悪い売上」を断ち切り、利益ベースでのLTVという長期的視点で事業を捉え、そして何よりも、一社一社、一人ひとりの顧客と真摯に向き合う組織文化を築き上げること。これなくして、どんな優れた戦略も真価を発揮することはありません。
最後に、これからのBtoBマーケティングを形作っていくであろう、重要な潮流に触れておきます。
コミュニティ・レッド・グロース (CLG: Community-Led Growth): これはPLGの進化形とも言える考え方で、ユーザー同士が交流し、学び合う「コミュニティ」を事業成長のエンジンに据えます。企業が一方的にサポートを提供するのではなく、ユーザー同士が助け合い、成功事例を共有する場を作ることで、①顧客維持率の向上、②製品改善のフィードバック源、③新規顧客獲得のチャネル、④サポートコストの削減といった、計り知れない価値が生まれます。
AI時代の内部データ活用: AIがマーケティングを完全に自動化する、という未来はまだ先かもしれませんが、その鍵を握るのが、各社が独自に保有する顧客の購買データやアンケート結果、財務データといった「内部データ」であることは間違いありません。この機密性の高いデータを、いかに安全かつ倫理的にAIに学習させ、パーソナライゼーションや需要予測の精度を飛躍的に高められるかが、将来の企業間競争を大きく左右するでしょう。
最後の第4章では、ここまで解説してきた基本的なBtoBマーケティングに大きな影響を与えつつあるデータを活用した「インテントマーケティング」と急速に進化しつつある「AIが与える影響」を解説します。
第4章:戦略思想を加速させる新たな燃料
ここまで、私たちはBtoBマーケティングという広大な海を航海するための基礎知識を学びました。BtoCとは全く異なる生態系、事業を成長させるための4つの強力な戦略思想(オーケストレーター、THE MODEL、ABM、PLG)、そして、それらの戦略を実践する上で避けては通れない組織の壁とその克服法。これでBtoBマーケティングの基本的な全体像は理解できたのではないかと思います。しかし、現代のBtoBマーケティングの海は、かつてないほど変化の潮流が速く、複雑になっています。顧客は営業担当者に会う前に、その購買プロセスの大半をオンラインで終えてしまいます。この「見えない検討期間」に、彼らが何に悩み、何を調べ、何を求めているのか。それを知ることができなければ、私たちの持つ多くの戦略は、宝の持ち腐れとなってしまいます。
「BtoBマーケティングの基本概要」の今回は、この「見えない検討期間」を可視化し、未来の顧客の行動を予測するための、2つの急速な潮流について深く掘り下げます。一つは、顧客の「意図(インテント)」を捉えるインテントマーケティング。もう一つは、その膨大なデータを解析し、マーケティング活動の全てを高度化する人工知能(AI)です。これらが、私たちが手に入れた4つの戦略思想にいかなる化学反応をもたらし、BtoBマーケティングを新たな次元へと引き上げるのか。その壮大な可能性と、具体的な活用法を解き明かしていきます。
インテントマーケティングとは何か?-「誰が」から「いつ、何を」へのパラダイムシフト
従来のBtoBマーケティングは、主に「デモグラフィック情報(業種、企業規模、地域など)」や「ファーモグラフィック情報(企業の財務状況や技術スタックなど)」に基づいてターゲットを定めてきました。これは、「どのような企業が我々の顧客になりそうか」という静的な属性に着目したアプローチです。しかし、この方法には大きな欠点があります。それは、ターゲットリストに載っている企業が、「今」自社の製品やサービスを検討しているとは限らない、という点です。
例えば、あなたが高性能なサーバーを販売する企業のマーケターだとします。ターゲットリストにある従業員1000名以上の製造業A社は、理想的な顧客像に合致します。しかし、A社がサーバーのリプレイスを検討するのは3年に一度かもしれません。タイミングがずれていれば、どれだけ熱心にアプローチしても、「今は必要ない」と一蹴されて終わりです。
ここに革新をもたらしているのがインテントマーケティングです。インテント(Intent)とは「意図」「目的」を意味します。インテントマーケティングとは、顧客がオンライン上で示す様々な行動データ(検索キーワード、記事の閲覧履歴、ホワイトペーパーのダウンロードなど)を分析し、「特定の課題解決や製品導入に対する“意図”や“関心”が高まっている兆候」をリアルタイムに捉え、その瞬間に最適なアプローチを行うマーケティング手法です。これは、顧客理解の軸を、静的な「Who(誰が)」に、「When(いつ)」「What(何を)」を加えて動的にシフトさせるものです。先ほどの例で言えば、製造業A社の情報システム部の誰かが、ここ1週間で「サーバー 耐用年数」「データセンター 移行 事例」「〇〇社(あなたの競合) サーバー 評判」といったキーワードで検索し、関連する複数の記事を読み込んでいる、という行動(インテントデータ)を察知できたらどうでしょうか。これは、A社がまさに今、サーバーのリプレイスを検討し始めたという極めて強力なシグナルです。この絶好のタイミングでアプローチできれば、商談化率は飛躍的に高まるでしょう。
インテントデータの源泉:3つの分類
インテントデータは、その収集元によって大きく3つに分類されます。
1. ファーストパーティ・インテントデータ(自社データ)
自社のWebサイト、ブログ、MAツール、CRMなど、自社が直接管理するプラットフォームから得られるデータです。
具体例:自社サイトの料金ページを3回以上閲覧した、特定の導入事例をダウンロードした、過去のウェビナーを視聴した、など。
特徴:最も信頼性が高く、具体的で質の高いデータです。自社の製品・サービスに直接的な関心を持つユーザーの行動であるため、購買意欲に直結しやすいと言えます。
2. セカンドパーティ・インテントデータ(パートナーデータ)
他社が収集したファーストパーティ・データを、パートナーシップを通じて共有・購入したものです。
具体例:自社製品と連携している他社ツールのレビューサイトで、自社製品との連携方法に関する記事を読んでいる、など。
特徴:自社の直接的な接点以外での顧客の動きを補完できます。特定の業界やテーマに特化したメディアとの連携などが考えられます。
3. サードパーティ・インテントデータ(外部データ)
自社とは直接関係のない、数百万ものWebサイト(業界ニュース、ブログ、レビューサイト、フォーラムなど)から、専門のデータプロバイダーが大規模に収集・分析したデータです。
具体例:ある企業の複数のIPアドレスから、特定のトピック(例:「サイバーセキュリティ」「サプライチェーン最適化」)に関するコンテンツの閲覧量が急増している、など。
特徴:市場全体のトレンドや、まだ自社を認知していない潜在顧客の初期段階の興味関心を幅広く捉えることができます。ただし、匿名化されたデータが多いため、解釈には専門的な知識やツールが必要です。
インテントマーケティングは、これらのデータを組み合わせることで、顧客の購買ジャーニーをより立体的に、そしてリアルタイムに浮かび上がらせるのです。
AIはBtoBマーケティングをどう変えるか?- スケールする「予測」と「個別最適化」
インテントマーケティングが「新たな燃料」だとすれば、その燃料から莫大なエネルギーを引き出し、マーケティング活動全体を次のレベルに押し上げるのがAI(人工知能)という「エンジン」です。AIがBtoBマーケティングに与える影響は、単なる業務効率化に留まりません。これまで人間の経験と勘に頼らざるを得なかった領域に、「予測」と「個別最適化(パーソナライゼーション)」という科学的なメスを入れ、その精度と規模を異次元に引き上げます。
AIがもたらす4つの変革
1. 予測リードスコアリングと需要予測
従来のリードスコアリングは、「役職が部長なら+10点」「資料請求をしたら+5点」といった、人間が設定したルールに基づいていました。しかしAIは、過去の膨大な成約・失注データを学習し、インテントデータを含む数百もの変数から、人間では気づけないような成約の相関関係を見つけ出します。そして、個々のリードが将来成約に至る確率を高い精度で予測します。これにより、営業チームは最も確度の高いリードにリソースを集中させることができ、組織全体の生産性が劇的に向上します。さらに、市場全体のインテントデータを分析することで、「来四半期、製造業でDX関連の需要が急増する」といったマクロな需要予測も可能になります。
2. ハイパー・パーソナライゼーションの実現
第1章で解説したように、BtoBの意思決定にはDMU(Decision Making Unit)と呼ばれる複数の人物が関わります。現場の担当者と経営者では、響くメッセージが全く異なります。AIは、ターゲット企業の業種や規模、そして個々の担当者の役職やオンライン上の行動履歴(インテントデータ)を瞬時に分析し、彼らの課題や関心事に完璧に合致したメッセージ(メールの文面、Webサイトの表示コンテンツ、広告のクリエイティブなど)を、大規模かつ自動的に生成・配信します。これはもはやセグメンテーションではなく、一人ひとりに語りかける「1to1コミュニケーション」のスケール化です。
3. コンテンツ生成と最適化の自動化
生成AIの進化は、コンテンツマーケティングのあり方を根底から変えつつあります。ターゲット顧客のペルソナとインテントデータをインプットするだけで、ブログ記事の草案、ホワイトペーパーの構成案、SNSの投稿文などを瞬時に生成できます。もちろん、最終的な仕上げは人間の専門家が行う必要がありますが、制作プロセスが大幅に短縮されることは間違いありません。さらに、過去のコンテンツのパフォーマンスをAIが分析し、「このトピックはエンゲージメントが高い」「このタイトルの方がクリック率が高い」といった改善提案を自動で行うことで、コンテンツの質をデータドリブンで継続的に向上させることが可能になります。
4. マーケティング・営業活動の自律的な最適化
AIは、実行した施策の結果を自ら学習し、次のアクションを最適化していきます。例えば、AIが「このタイプの顧客には、このタイミングで、この内容のメールを送るのが最も効果的だ」と判断し、MA(マーケティングオートメーション)ツールを自動で操作する。あるいは、営業担当者のカレンダーを分析し、「A社の〇〇部長は、火曜日の午前中にオンライン会議の承諾率が高い」と予測して、アポイント調整を提案する。このように、AIはマーケティング・営業プロセス全体に自律的なPDCAサイクルを埋め込み、人間をより創造的で戦略的な業務に集中させてくれるのです。
新潮流は、基本のBtoBマーケティングにどう影響を与えるか?
インテントマーケティングとAIマーケティングは、単なる新しい戦術ではありません。第1章で解説したBtoBマーケティングの根源的な特性(6つの決定的差異)そのものの捉え方を進化させ、陥りがちな罠を回避するための強力な武器となります。
顧客(Customer)の解像度向上:「組織の合理」を形成するDMUの特定が、これまで以上に精緻になります。インテントデータは、公式な役職だけでは見えなかった「隠れたインフルエンサー(技術評価の中心人物など)」を、そのオンライン行動からあぶり出すことを可能にします。AIは、その多様なDMUのメンバー一人ひとりに対して、最適なメッセージを自動で届けることを可能にし、複雑な合意形成プロセスを円滑化します。
関係性(Relationship)の深化:顧客との関係性は、「何かあってから対応する」リアクティブなものから、「何か起こる前に察知して提案する」プロアクティブなパートナーシップへと進化します。AIが顧客の製品利用データやインテントデータを常時監視し、「解約の兆候」や「新たな課題の発生」を予測します。これにより、カスタマーサクセスは問題が深刻化する前に先回りしてサポートを提供でき、顧客からの信頼をより強固なものにします。
価値連鎖(Value Chain)の可視化:サードパーティ・インテントデータを活用することで、「顧客の顧客」が今何に関心を持っているかを把握できるようになります。これにより、「貴社の大口取引先であるB社が今、サステナビリティに関する情報収集を活発化させています。弊社のこのソリューションは、貴社の製品の環境負荷を低減し、B社への提案力を高めることに直結します」といった、より大局的で説得力のある価値提案が可能になります。
「ターゲットの罠」からの脱却:アプローチすべきは、静的な属性で定義された「組織」ではなく、課題解決の「意図」が生まれた瞬間です。インテントマーケティングは、まさにその「購買意欲のビッグバン」の瞬間を捉えることを可能にし、マーケティングと営業のあらゆる活動を、無駄弾のない、極めて効率的なものに変えます。
「時間軸の罠」の克服:「打ち上げ花火」で終わらせないためのリードナーチャリング(顧客育成)を、AIが超長期的に、かつ、きめ細やかに実行します。AIは、各リードの関心度の変化をインテントデータから読み取り、数ヶ月、時には数年にわたって、最適なタイミングで最適な情報を提供し続け、関係性を途切れさせません。
4つの流派は、インテントとAIでどう進化するか?
インテントマーケティングとAIマーケティングは、私たちが第2章で学んだ4つの戦略思想(流派)を陳腐化させるものでは決してありません。むしろ、それぞれの流派が持つポテンシャルを最大限に引き出し、その効果を増幅させるブースターとして機能します。
1. オーケストレーター型 × インテント & AI
オーケストレーター型の指揮者(CMOやCEO)は、「未来を予測する楽譜」を手に入れることになります。AIによる市場全体の需要予測は、どの市場にリソースを投下すべきかという、事業戦略レベルの重要な意思決定を支援します。インテントデータは、顧客という聴衆が今まさに聴きたがっている曲(解決したい課題)をリアルタイムで教えてくれます。これにより、指揮者は勘や経験だけに頼るのではなく、データという客観的な根拠に基づいて、開発、マーケティング、営業、カスタマーサクセス(CS)という各楽団員に的確な指示を出し、市場のニーズと完璧に調和した、より感動的な顧客体験という名のシンフォニーを奏でることができるようになります。
2. THE MODEL型 × インテント & AI
再現性ある成長を目指す「顧客創出の工場」は、スマートファクトリーへと進化します。
マーケティング(材料調達):インテントデータを活用し、「今、購買検討している可能性が高い」という最高品質の材料(リード)だけを効率的に仕入れることができます。これにより、後工程の負担が大幅に軽減されます。
インサイドセールス(検品・加工):AIによる予測リードスコアリングが、ベルトコンベアを流れてくる大量の材料の中から、最も価値の高いもの(ホットリード)を瞬時に見つけ出し、優先順位を付けてくれます。これにより、インサイドセールスは最も実りの多いアプローチに集中できます。
営業/フィールドセールス(組立):AIが、ターゲット顧客のインテントデータに基づき、「この顧客は価格よりもサポート体制を重視している」「競合の〇〇社と比較検討している可能性が高い」といったインサイトを提供。営業担当者は、相手の心に響く、パーソナライズされた提案を携えて商談に臨むことができます。
カスタマーサクセス(品質保証):AIが製品利用データなどから「解約の兆候」を予測し、アラートを発します。これにより、受動的な対応ではなく、プロアクティブな働きかけで顧客の成功を支援し、LTVを最大化することが可能になります。
3. ABM型 × インテント & AI
戦略的な一本釣り漁師は、GPSと魚群探知機を搭載したハイテク漁船を手に入れます。
ターゲットアカウントの活性化検知:ABMの最大の課題は、「いつ」アプローチすべきか、でした。インテントデータは、ターゲットリスト(例:100社)の中から、今まさに自社に関連する情報収集を活発化させている「旬の魚(アカウント)」がどれかを教えてくれます。これにより、リソースを最も可能性の高い企業に集中投下できます。
DMUへの網羅的アプローチ:AIを活用し、ターゲットアカウント内の様々な部署、役職のキーパーソンに対して、それぞれの立場に合わせたパーソナライズド広告やメールを自動で配信。アカウント全体を多角的かつ継続的に攻め落とす、高度な「デジタル・エアカバー(空中支援)」が可能になります。営業担当者が地上戦を仕掛ける前に、AIが空から絨毯爆撃を行い、地ならしをしてくれるイメージです。
4.PLG型 × インテント & AI
製品自身が最高の営業マンとなるPLGモデルは、顧客の心を読める営業マンへと進化します。
Product-Qualified Lead (PQL) の高度化:PLGでは、製品内での行動(例:「有料機能を試した」)に基づいて有望なユーザー(PQL)を特定します。ここにインテントデータを組み合わせることで、解像度が格段に上がります。例えば、「製品内でチーム管理機能を試した」ユーザーが、同時に社外のWebサイトで「エンタープライズ向け セキュリティ要件」について調べていたらどうでしょうか。これは、個人利用から組織的な本格導入へと検討フェーズが移行した極めて強力なシグナルです。
プロアクティブなアップセル/クロスセル:AIが個々のユーザーの製品利用パターンとインテントデータを分析し、「このユーザーは次に〇〇の機能に関心を持つ可能性が高い」と予測。製品内で最適なタイミングで、チュートリアル動画を表示したり、上位プランへのアップグレードを促したりといった、パーソナライズされた働きかけを自動で行い、LTV向上に貢献します。
まとめ
この長編にわたる解説は、私・西口個人のFacebook上での繋がりの中で、BtoBマーケティングに関する発信に興味を持ってくださる方が多いことに気づいて、BtoBに関する最も基本的な概念と概要を、私の実務でのメモや走り書きを編集したものです。全4回を編集し終えて、あらためて確信したことがあります。それは、どれだけデータが精緻になり、AIが賢くなろうとも、BtoBマーケティングの根幹にあるものは決して変わらない、ということです。
その根幹とは、「一社の顧客の、事業の成功に、どこまで深く、自分事として、真摯に寄り添えるか」という人間的な問いです。インテントデータは顧客の「意図」を教えてくれますが、その奥にある「悩み」や「情熱」までを語ってはくれません。AIは最適なメッセージを生成できますが、パートナーとしての「信頼」を築く温かい対話はできません。テクノロジーは、あくまで顧客をより深く理解し、より良い関係を築くための「手段」であり、それ自体が「目的」になることは決してありません。私たちが目指すべき未来は、テクノロジーによって効率化された「無機質な世界」ではなく、テクノロジーによって時間と創造性を手に入れた人間が、顧客一人ひとりと、より深く、より人間的に向き合えるようになる「共感のスケール化(Empathy at Scale)」が実現された世界だと思うのです。
これを皮切りに、BtoBマーケティングに関しても、書き溜めているメモや走り書きを生成AIで編集しながら、Wisdom-Betaで、今後も継続して発信していきます。この解説が、もし役立ちそうな方がいらっしゃれば、ぜひシェアしていただければと思います。もちろん、批評、コメント添えて、転載していただいても問題ありません。ここまでお読みいただいてありがとうございました。
まだ会員登録されていない方へ
会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です

